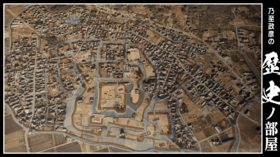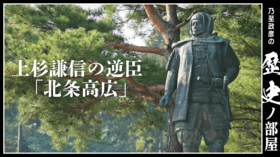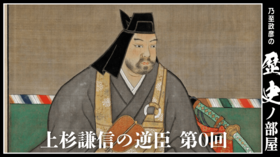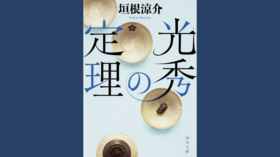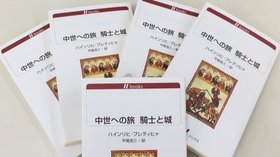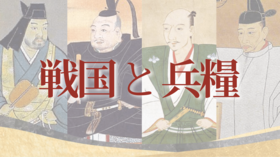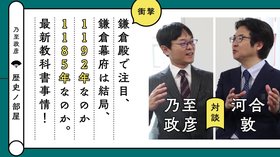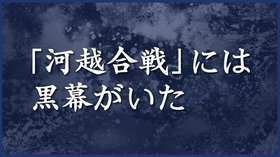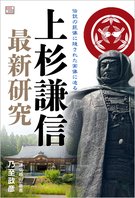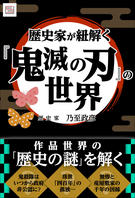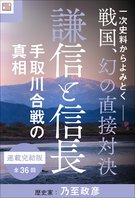近年様々な復元案が出される安土城。
その派手さから、織田信長の権力を象徴する城という見方が一般的である。
今回は「謙信と信長」連載中の歴史家・乃至政彦が「安土城」を解説。
権力の象徴としての安土城に対する疑問を出発点に、築城意図の別の可能性について乃至氏の考えを聞く。
・先駆的だった安土城
・安土城は隠居の城
・派手すぎる安土城で行われた「御馬揃え」
・乃至政彦が考える「安土城の意味」
〈一部抜粋〉安土城は隠居の城
織田信長は自ら擁立した将軍・足利義昭を京都から追放しました。
安土城はそれからしばらくして造られたお城です。天正4年に築城し、そこから亡くなるまでの約6年間を安土城で過ごしたとされています。
このお城は破格のお城です。近世のいわゆる天守閣の先駆けとなる画期的なお城でした。
お城と言えば天守閣を想像すると思うんですが、その象徴となる天守を作ったのが安土城。
それ以前にもあると言われますけど、時代の転換を示す象徴的な建築物は安土城だったと思います。
安土城にはさまざま復元案が出ています。しかし本当の形はいまだわかっていません。かなり派手なお城というのは間違いないのですが。
そのため安土城は信長の権力の象徴として作ったと言われています。
しかし建築物で自分の権力を固辞する方法は信長以前にはそう多くないのです。かろうじて思い浮かぶのは足利義満が建てた鹿苑寺。いわゆる金閣寺でしょうか。
他方で安土城築城時に信長が考えていたのは家督を次の世代に譲り渡すことです。
安土城築城前、信長は美濃の岐阜城を居城としていました。これを息子・織田信忠に譲り渡して自分は安土に移ろうとしたわけです。
そのために建てられたのが安土城。織田家の本城としてではなくいわば隠居の城です。
例えば春日山城を拠点としていた上杉謙信の父・長尾為景は、晩年期には中郡の三条城に移ってということがいろんな資料に書かれています。
ということは三条城は為景の隠居の城だと考えられます。
安土城も同様に信長の隠居の城だったとも考えられます。
【高澤等×乃至政彦対談】「天才」「中世壊して」「残虐」ではない。新たな織田信長像に迫る。
織田信忠の屋敷跡が示すこと
しかし隠居の城としては派手すぎですね。どう見ても天下無双の城です。
フロイスもこんな城は見たことがないと絶賛するぐらいとんでもないずば抜けた城。見た目からしておかしいです。
しかも信長は贅沢を好まない人です。贅沢を凝らして酒池肉林を楽しむタイプではありません。
逆に足利義満は綺麗なお稚児さんをいっぱい並べて行列を伴って嫉妬を買うということが好きな人です。
また安土城には羽柴秀吉や前田利家の屋敷跡など、いろんな屋敷跡があるということが江戸時代に伝わっています。
この中には信長の息子たちの屋敷跡もあるんです。
しかも徳川家康の屋敷跡まであります。
武井柚庵や柴田勝家クラスだったらまだわかるけど徳川家康クラスでもあるんですね。ということは諸大名がそこに居住できる城を作ったということです。
信長は美濃と尾張を織田家の本領と認識し、岐阜城を信忠に譲りました。
にもかかわらずこれを上回る権威の城を作ってどうするんだというのが私の疑問です。
もし信長が天正10年ではなく別の年に亡くなったとして、信忠が安土城に移るでしょうか。
信忠は美濃と尾張を織田の本家として預かっている、預かっているというのは自分の領土として持っている。これをさしおいて近江に移り織田家本領から外れるのは考えにくいです。
また安土城には信忠の屋敷があるわけですから、信忠の居城になるということはあまり想定されていなかったと思います。...続きは音声配信で。
...