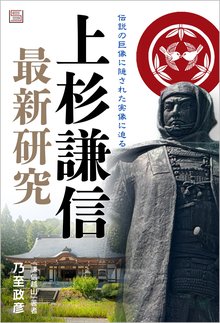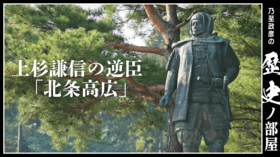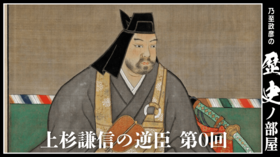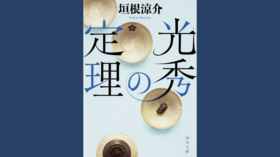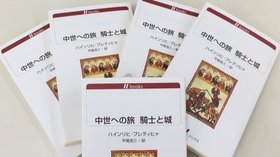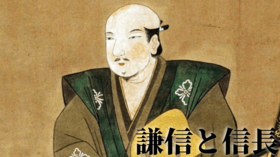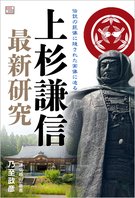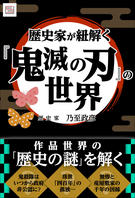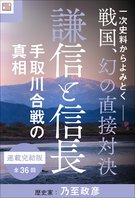連戦連敗のデータから「戦国最弱」と呼ばれる武将・小田氏治。あまり有能ではないイメージが定着しつつある。だが、本当に弱い武将が何度も大きな合戦にチャレンジできるのだろうか。本連載では有名な戦績データがどこまで事実であるかを確かめながら「小田氏治」の実像に迫りなおす。
上杉軍の後退で小田氏と佐竹氏の緊張が高まるなか、1569年に勃発した手這坂合戦。急襲と迎撃、そして小田城陥落までの攻防を、一次史料から実像に迫る。
歴史家。著書に『戦国大変 決断を迫られた武将たち』『謙信越山』(SYNCHRONOUS BOOKS)、『上杉謙信の夢と野望』(KKベストセラーズ)、『平将門と天慶の乱』『戦国の陣形』(講談社現代新書)など。書籍監修や講演活動なども行なっている。1974年生まれ。高松市出身、相模原市在住。
佐竹義重との抗争激化
上杉輝虎が関東から撤退し、再度の遠征が難しくなっていく中、小田氏治は佐竹義重、および大掾貞国(永禄5年より当主)・真壁久幹たちとの緊張関係が続いていた。
永禄11年12月、相模国の北条氏康は輝虎と停戦して和睦する交渉を開始。
輝虎は関東の戦線から離れて、武田信玄との抗争および北陸への進出に意欲を見せ始めた。
ここに、もともと上杉陣営だった関東諸士は、強力な後ろ盾を得ることが不可能になってきた。
このため、氏治と佐竹は両者の紛争を自分たちの実力で解決しなければならなくなってくる。
その緊張が頂点に達したのが、永禄12年(1569)1月の佐竹軍による小田領侵攻と、11月の手這坂(てばいざか)合戦である。
ちなみに手這坂という地名がどこなのかは、近世から議論があるものの、近年の研究では、八郷町史編さん委員会の『八郷町史』(八郷町、2005)が、石岡市小幡の「小字(こあざ)手葉井(てばい)」に比定した。
千葉篤志氏は、この手葉井が、旧八郷町から筑波山を超える風返峠登り口の小道であることを指摘。
そこを使って進撃してきた氏治を、真壁久幹および梶原政景を中心とする佐竹陣営が小幡を「迎撃する場所」として選んだものとする。
さて、当地で起きる合戦までの経緯と合戦そのものを史料に見ていこう。
手這坂合戦までの経緯
永禄12年(1569)1月15日、紛争は例の海老ヶ島城から激化した。
佐竹陣営が海老ヶ島城を攻めたのである。城は翌日夜(「酉刻」午後五時から七時頃)から猛攻を加えられて、17日午刻(正午)までに巣城のみを残すだけとなった(上杉家文書/『大日本史料 第十編之一』九二三〜四ページ文書)。
ここで「城主(平塚刑部太輔)頻而懇望」により、3日の交渉があった後、制圧された。
佐竹軍は証人を集めて受け取り、21日には小田城に迫った(太田道誉書状/山吉文書。多賀谷祥連[政経]書状/『土浦市資料集 土浦関係中世史料集 下巻』一八七ページ文書)。
この小田城攻めにおいて、5月15日に佐竹軍が渡河してきたため、氏治はこれに立ち向かった。
そして「一日之内三度仕合、敵数多討留坊戦任存分候」と、その日のうちに三度交戦して、思い通り敵を多数討ち取ったことを、那須資胤に宛てた書状で誇っている(那須文書「小田氏治書状」/『土浦市史資料集 土浦関係中世史料集下巻』一八七〜八ページ文書)。
その後、佐竹軍は帰陣した。
この1月から5月または閏5月までの佐竹軍と小田軍の戦いは、結果としては佐竹軍が海老ヶ島城を占領する戦果を挙げて終わった。
だが、氏治は小田城を約4ヶ月守り通して、ついには野戦で佐竹軍を打ち払い、本拠地だけは守り通した。
どちらも勝利したとは言い難いが、それぞれの意地は押し通したと言えるだろう。
手這坂合戦の勃発

そして、その約半年後──、運命の時が迫ってきた。...