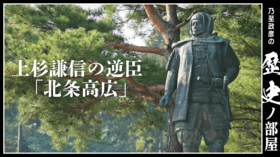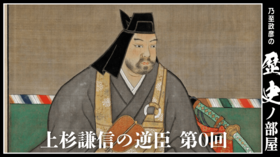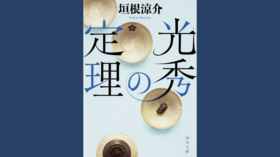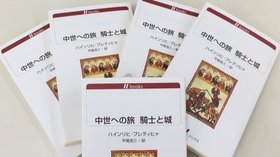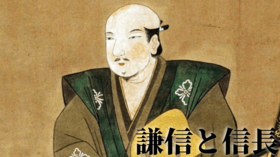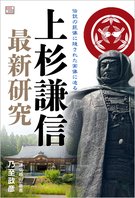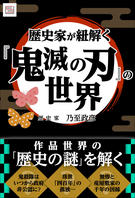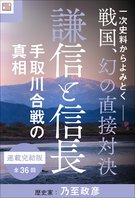常陸の不死鳥と呼ばれる戦国大名・小田氏治。本連載第10、11回でも触れたように海老ヶ島合戦前夜、氏治の作戦は敵方に看破されていた。
ただ、もし氏治の作戦が順調に進んで、結城政勝を打ち破っていたら、北条氏康に攻められていた安房国の里見義堯も反攻に出られたかもしれない。武蔵国の太田資正も史実より早く氏康を裏切る展開があってもおかしくない。
小田氏治は侮れない。
海老ヶ島ではないどこか別のところで戦端が開かれていたら、関東の勢力図が大きく塗り変わっていた可能性がある。
結城政勝と小田氏治の会戦は、ある意味では戦国関東の天下を定める戦いでもあったのだ。
歴史家。著書に『戦国大変 決断を迫られた武将たち』『謙信越山』(SYNCHRONOUS BOOKS)、『上杉謙信の夢と野望』(KKベストセラーズ)、『平将門と天慶の乱』『戦国の陣形』(講談社現代新書)など。書籍監修や講演活動なども行なっている。1974年生まれ。高松市出身、相模原市在住。
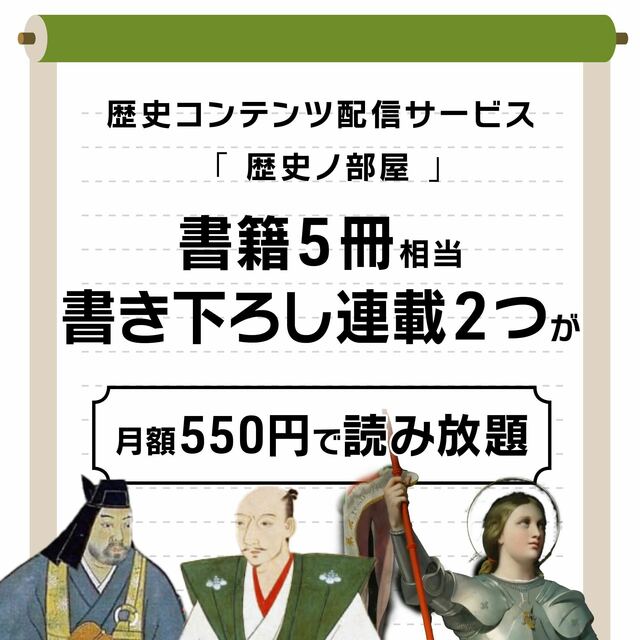
海老ヶ島合戦の内容
弘治2年(1556)4月5日、海老ヶ島合戦が始まる。
昨年に関東公方の足利晴氏と、山内・扇谷の両上杉(上杉朝定・上杉憲政)連合が、現地武士層が「南方衆」として反発していた北条氏康に戦争を仕掛けて惨敗する「河越合戦」があった。関東の勢力図は大きく塗り変わっていた。晴氏が降参すると、それまで反北条派に与していた者たちも「特に悪気はありませんでした。晴氏さまの思うままに」とばかりに、親北条陣営に鞍替えを開始していた。
だが、常陸国から公方連合軍に援軍として菅谷隠岐守を派遣していた小田氏治はこの流れに乗っていなかった。
対する結城政勝は、氏康の傘下に属することを表明して、その支援を取り付ける。
しかし河越合戦の経緯から、氏康の参戦を警戒する氏治は、佐竹義昭と示しあわせて、北条軍がこちらにやってこないよう工作を進めていた。それは順調に進んでおり、この戦いは本来なら小田氏治vs.結城政勝の対決となるはずだった。
もしそうなれば、開戦時期と戦場は氏治が主導して決定し、政勝を打ち破る可能性は低くなかっただろう。
ところが白河晴綱を中心に、政勝や氏康らも氏治の計略を見抜くこととなり、氏治の計画は破綻した。
結城軍には、相模国の北条氏康500騎、武蔵国の太田資正、多賀谷政経が味方した。さらに下総国の公方・足利義氏も簗田・一色・野田左衛門大夫ら3000余騎を援軍に派遣した。
氏康は2月下旬に相模国鎌倉を経て武蔵国江戸と下総国に着陣。海老ヶ島を目指した。
北条軍と合流した政勝は、早速小田領海老ヶ島城に侵攻する。続けて北条家臣の遠山丹波守・冨永(三郎左衛門尉政家)も500騎で海老ヶ島に着陣した。
これを知った氏治は、急ぎ迎撃に向かう。

小田軍と結城軍はこの小貝川を挟んで対峙、当時はより大きな河川だったと思われる
海老ヶ島城に馳せ参じた小田軍2000騎
結城方が攻める海老ヶ島城は、水の城である。...