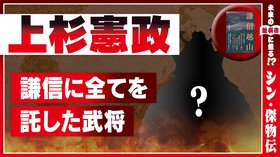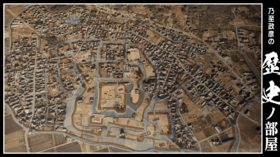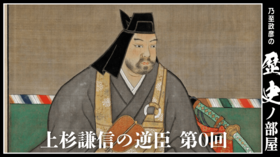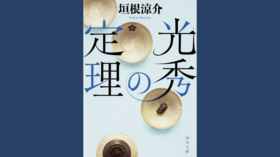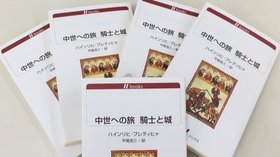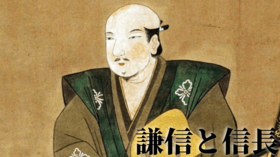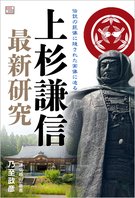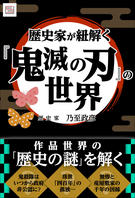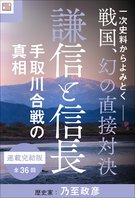『謙信越山』著者・乃至政彦が挑む「御館の乱」と「上杉景虎」。上杉家のみならず、北条・武田など関東の戦国史に多大な影響を与えた越後の跡目争いを上杉景虎(北条三郎)を中心に見ていく(全5回の第3回)
今回は上杉謙信の一代記として信頼性の高い『松隣夜話』をはじめとするいくつかの史料をもとに、上杉景虎の人物像と、上杉家の家督争いの実像を整理していく。
歴史家。著書に『戦国大変 決断を迫られた武将たち』『謙信越山』(SYNCHRONOUS BOOKS)、『上杉謙信の夢と野望』(KKベストセラーズ)、『平将門と天慶の乱』『戦国の陣形』(講談社現代新書)など。書籍監修や講演活動なども行なっている。1974年生まれ。高松市出身、相模原市在住。
越相同盟の解消
北条氏康が病死すると、氏政は信玄との同盟を回復します。
これを見た謙信は氏政と手切れします。なお、軍記物には氏政が氏康の遺言で謙信ではなく信玄との同盟を復活させたと伝わりますが、当時の史料にそうした記録は見られません。むしろ、氏康の方針から離れて、氏政自身が主体的に判断したものではないかと思われます。
元亀元年8月:上杉と武田が再び敵対化します。
同年10月:上杉謙信と徳川家康が反武田同盟を締結します。
元亀2年(1571):この年、上杉三郎景虎に長男・道満丸が生まれます。謙信には初孫で、次代を担う後継者の誕生でした。
同年4月:武田と北条が再び和睦するとの情報が謙信の元に入り、謙信は氏康に事実を確認します。
同年11月:北条氏康が病死します。
同年12月:武田と北条の同盟が復活し、謙信と手切の一札を送り合います。
さて、この間、景虎は越後で遊んでいたわけではなく、ちゃんと謙信と一緒にその旗本に同陣していました。
北条との同盟が決裂した後、景虎は越後に戻ることはありませんでした。すでに彼のもとには越後生まれの子供たちがいました。長男・道満丸です。謙信にすれば初孫であり、やがて上杉家を継ぐ者だったと見られていたに違いありません。
天正2年(1575)12月:謙信が剃髪し、高野山無量光院と師檀関係を結び、法印大和尚となります。
天正3年(1576)1月:謙信は長尾顕景に弾正少弼の官途を譲り、上杉景勝へと名乗りを改めさせます(史料C・D・E参照)。
同年2月:上杉家に「御軍役帳」が作られ、「御中城様」の景勝が最上位に置かれました。謙信と景虎の名前はなく、その側近も見られません(史料F参照)。
同年4月:謙信が普光寺(南魚沼市)に願文を捧げます。その内容は、「当家分国」に手出しし、「誓詞」を翻して、「三郎(景虎)ならびに不限代忠信仕来遠山父子差捨」てたうえ、氏康の「遺言」に叛いて同盟を破棄し、「東将軍」(足利藤政)を「切腹」させた北条氏政を「退治」するべきだと主張するものでした。しかし、その後、謙信が北条軍と干戈を交えることはありませんでした。なぜなら、信長から京都を逐われた将軍・足利義昭が「越・甲・相和之儀」(上杉・武田・北条の和睦)を調えて、自身の京都帰還に「馳走」するよう要請してきたためであり、これより謙信は進出先を関東から北陸道へ改め、信長との対決姿勢を固めていきます。
ただ、景虎はのちに御館の乱が勃発したときも、上杉流の手紙ではなく北条流の手紙の書き方をしています。彼が政治権力の中枢に関わる業務をほとんど学ぶ時間を得られなかったと思われます。
さて、謙信は景虎に上杉の名字を継がせましたが、天正3年(1575)にはもう一人の養子である長尾喜平次顕景にも上杉の名字を名乗らせ、さらには弾正少弼の官途まで与えます。
上杉弾正少弼景勝の誕生です。
景勝はここで謙信の軍役帳に「御中城様」と記されます。気になるのは、越後上杉家の当主を意味する「御屋形様」やその上に当たる謙信の敬称「御実城様」ではなく、まったく新しい敬称で呼ばれているところです。
これだけを見ると、謙信の後継構想は単純なものではなかったと思われます
少なくとも、景勝は正当後継者ではないでしょう。
とはいえ、景虎もそのように育成されていません。
謙信は、景勝には実戦経験を豊富に積ませていました。側近たちも景勝と親しい者が多かったようです。
そこをよく考えると、謙信は「いまは保留」という気持ちが強かったのかもしれません。勢力図や政局は常に変わる不安定な時代でしたから、これは必ずしも愚策とは言い切れません。臨機応変は当時もっとも重要な対応でした。

謙信と家督
さて、ここで謙信の家督に対する考え方を見てみましょう。...