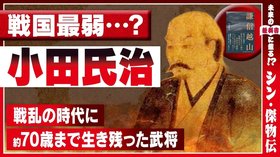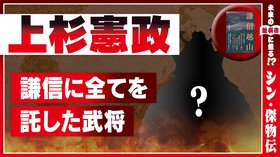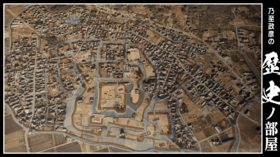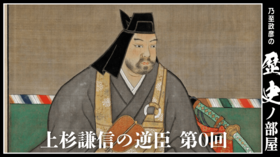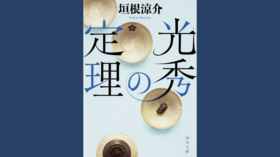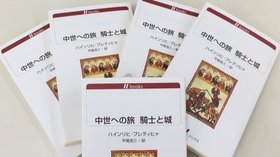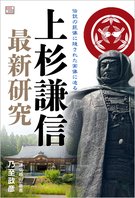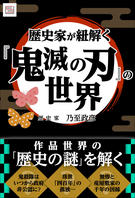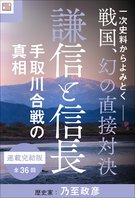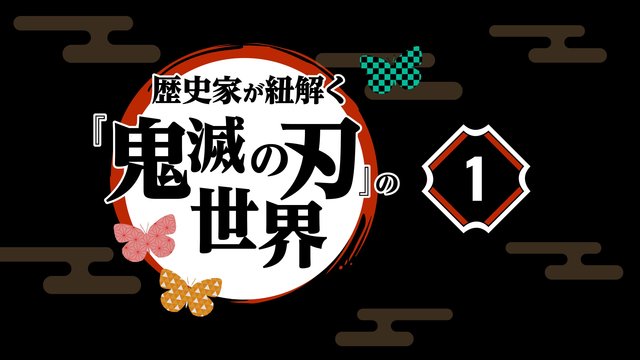
この夏、劇場版「無限城編」が公開される『鬼滅の刃』。シンクロナスのコンテンツ「歴史の部屋」でお馴染みの乃至政彦さんが、歴史家ならではの視点で、作品世界の「歴史の謎」に挑みます。
最終回に登場した『善逸伝』は、本当に善逸が書いたのか?鬼殺隊はなぜ「非公認」のまま活動できたのか?無惨のあの「パワハラ会議」に、実は超合理的な戦略が隠されていたとしたら?物語最大の謎、無惨と産屋敷家の千年の因縁の起源とは? 最強の鬼・無惨が、なぜついに「千年王国」を築けなかったのか……。
作品を愛する著者が、歴史という補助線を引くことで導いた考察をお楽しみください。
この記事には『鬼滅の刃』第23巻に掲載されている最終話のネタバレが書かれています。未読の方はご注意ください。
はじめに
『鬼滅の刃』は、何度読んでも新しい発見がある、本当に面白い物語である。
家族や仲間を想う心、困難に立ち向かう意志の強さに胸を打たれる一方で、読み終えた後、ふと「あれはどういうことだったのだろう?」という、心地よい疑問符が心に残る。
歴史業に関わる私も、皆さんと同じ一人のファンにすぎない。ただ職業柄、物語の“行間”に隠された歴史や背景を、つい探ってしまうクセがある。
歴史研究で使う謎解きの道具を片手に、この壮大な物語の世界で本気で遊んでみよう──というのが、本書の始まりである。本書の元となった一連の原稿は、あくまで個人の趣味が高じたものだが、どうせなら読者の皆さんとこのワクワクを共有したい。そんなサービス精神と、ささやかながら作品解釈への貢献を願って書き進めた。
本書では、作品世界の「歴史の謎」に挑んでいく。
最終回に登場した『善逸伝』は、本当に善逸が書いたのか?
鬼殺隊はなぜ「非公認」のまま活動できたのか?
無惨のあの「パワハラ会議」に、実は超合理的な戦略が隠されていたとしたら?
そして、物語最大の謎、無惨と産屋敷家の千年の因縁の起源とは? さらには、最強の鬼・無惨が、なぜついに「千年王国」を築けなかったのか……。
本連載の考察は、歴史という補助線を引くことで見えてくる、一つの解釈にすぎない。これが絶対の正解だと言うつもりは毛頭ない。ぜひ軽い気持ちでページをめくり、皆さんも自分だけの「?」を見つけて、謎解きの旅を楽しんでいただければ幸いである。
※なお本連載は、著者が個人的な趣味で執筆したものであり、原作漫画の出版社である株式会社集英社、ならびにアニメ製作関係各位とは一切関係ありません。
『善逸伝』という歴史資料
人気漫画『鬼滅の刃』の最終回には、重要人物のひとり・我妻善逸(あがつまぜんいつ)の名前を冠した和綴(わとじ)の文献が登場する。
その外題(げだい/題名、表題、タイトル)は、そのままずばり『善逸伝』だ。
名前から善逸の一代記と推定できる(この時代の実録は、それ以外の内容で、こういう題名にすることは原則として無いため)。一連の事件を叙述した歴史資料であるに違いない。
しかしその実態は謎だらけである。その具体的内容がどのようなものであるか本編でいっさい紹介されていないためだ。
ずっと我妻家に保管されていたようだが、誰が何のために書いたのかわからない。一読者として好奇心を大いに擽られるところだ。
私が稼業とする歴史研究の手法で探れば、連載の最終回で披露された情報だけで、その内容をいくらか想像できそうに思う。
たとえば『善逸伝』を歴史資料として眺めると、重要な情報が3点ほど認められる。まずこれらを分析して、その実相をある程度まで絞り出し、最後にそこから導き出される私見を述べることとしたい。
壱ノ鍵:《外題》──作者は我妻家の者
一つ目の情報は『善逸伝』という外題だ。ここには、作者を特定する手がかりが隠されている。
まず外題から言えることは、これが善逸の伝記であることだろう。また、それと同時に、善逸本人による自伝(自叙伝)ではないことも指摘できよう。
なぜかと言うと、善逸が読み書きを学んだであろう明治末期から大正初期にかけて、自叙伝の外題は、それとわかる名称がつけられていたからである。
同時代の例をあげれば、福沢諭吉『福自伝』、徳富蘇峰『蘇峰自伝』、高橋是清『高橋是清自伝』、大杉栄『自叙伝』、横山大観『大観自叙伝』などがある。いずれも自伝とわかる外題となっていよう。もし『善逸伝』が自伝なら、『善逸自伝』という形式の外題に落ち着いていたはずである。
ここで、同書が我妻善逸の伝記ではあるが、本人が書いた作品でないらしいことが見えてくる。
さらに追及しよう。無名人物の一代記を外部向けに書くとき、その外題にその人とわかるようフルネームが冠せられる。織田信長クラスの有名人なら『信長公記』という外題もありえるが、善逸のような人物を主人公とする外部向けの伝記なら『我妻善逸伝』とするのが普通だ。それがなぜか『善逸伝』となっている。ここから、この伝記の想定読者が見えてくる。これは、我妻家が子々孫々にわたり、太祖たる善逸の事蹟を内部に語り残していくため作られたと考えられるのだ。
ちなみに、善逸が自分を伝説の勇者らしく演出するため、自らこの伝記を書き上げて、この外題にした可能性を想像する人もいると思うが、たぶんそれはありえない。われわれは『○○(個人名)伝』という題名に接すると、ヒロイックな主人公の偉大な物語を想像しがちだが、それはそうした娯楽作品が増産される時代の受け止め方で、善逸が生きた時代の感覚ではないはずだからだ。
したがって『善逸伝』の作者は、善逸ではなく、別の人物であり、それは我妻家の誰かである可能性が高いと言える。
弐ノ鍵:《筆力》赤点高校生でも熱読可の秘史
歴史文献『善逸伝』の本文にどういうことが書かれているかを探ってみたい。本文が不明でも内容を探る方法はある。皆さんも書籍の現物が入手できないとき、書評からその内容を思い浮かべることがあろう。これと同様に、我妻善照(あがつまよしてる)少年の反応からその内容を想像してみるのだ。
善逸の曽孫と思われる善照少年は、「こないだも赤点ばっかりだったでしょ!!」と姉の燈子(とうこ)に叱られるぐらい勉強が苦手である。平成生まれのどこにでもいる、すけべな高校生と言えるだろう。そんな善照少年が、自宅の物置近くで『善逸伝』を読み、落涙していたのだから、同書は古典に通じていないと読みにくい草書体でなく、現代人が見慣れた楷書体で書かれていたと考えていいだろう。
同書を半ば辺りまで読んだ善照少年は、「凄ぇ!! みんなで鬼のボス倒したじゃん!! やったじゃん!!」とボロ泣きした。この反応から『善逸伝』は、「鬼のボス」を普通では倒せない強敵として、登場人物である「みんな」を感情移入しやすい味方として描いているのは間違いない。燈子も同書を「ひいおじいちゃんの嘘小説」と呼んでいることを併せて考えると、文芸性の強い伝記に仕立てられていたのだろう。
これら善照少年を感動させたところは、ご先祖さまである善逸自身が、それぞれの人間や鬼たちに対して抱く想いがそのまま反映されていよう。「全集中・常中」を習得させるため、善逸を「一番応援」したという胡蝶しのぶについても詳述されていることと思う。
ただ、「鬼」およびそれを狩る「鬼殺隊」の存在は、古来より双方が世間に隠匿し続けてきた非公開情報であった。いくら「最後の鬼」を倒し、その組織が解体されたにしても、戦死者たちの覚悟と最期を想うと、関係者たちは他言することを控えたに違いない。伴侶が一時期「鬼」だった事実のある善逸翁もまた同じ想いだったはずだ。
しかし同書は文芸的な性格を色濃く残して、前半にその顛末を詳述した。これは何者かの強い熱意によって、このくだりを子孫たちに読んでもらうため、物語を紡いだことを示していよう。ただ、この前半にある「最後の鬼」を退治するための物語とするならば、外題は「最後の鬼を退治する物語」を意味するものでも良かったはずである。例えば『無惨退治記(意味:最後の鬼である無惨を退治した記録)』とか『我妻物語(意味:我妻という人のお話)』『鬼滅奇譚(意味:鬼を滅ぼす不思議なお話)』になっていたとして不思議はない。
だが、同書の外題はあくまで『善逸伝』なのである。
参ノ鍵:《装幀》和綴本なのに横書きである謎
最後の鍵は、その装幀である。『鬼滅の刃』最終回がお手許にある方は、善照少年が『善逸伝』を読んで泣いているコマを見てほしい。そこに2つないし3つの特徴を読み取れる。お気づきになられただろうか。
まず、なぜこの時代に和綴本なのかという謎である。同書が書かれたのは、西洋文化が日本に流れ込んで半世紀近く経った大正前期以降である。その時代に何者かが子孫に書き伝えるものがあったとして、それをわざわざ和綴本にするだろうか。すでに手製の和紙よりも機械製の洋紙の方が大きな需要を占めており、和綴本は希少と化していた。製本技術も西洋式が一般化していたであろう。なのに、『善逸伝』はなぜか和綴本として装幀されている。
ついで、重箱の隅を衝くわけでもないが、外題の『善逸伝』が旧字体ではなく、新字体で書かれている謎である。大正時代から昭和初期にかけて成立した手製の本なら、ここはやはり『善逸傳』と書かれるべきであろう。
そして最後に、『善逸伝』が読まれているコマを改めて見直してほしい。同書が縦書きの場合、その外題は善照少年の右手が触れる部分にあるべきである。ところがこれがそうではなく、なぜか左手のところに書いてある。
つまり、裏表紙の部分だ。ジャンプコミックスの単行本で言うなら、中身は縦書きで、例えば『鬼滅の刃』23巻の場合、右手はおもて表紙にある竈門兄妹の笑顔に、左手は無機質なデザインの裏表紙に触れることになる。これが横書きの書籍だと、おもて表紙と裏表紙は逆になる。つまり、善照が読んでいる『善逸伝』は、横書きの本である可能性が高いのだ。
このように装幀の謎を考えると、『善逸伝』は、面倒にもわざわざ和綴本の装幀を選んでおり、その成立時期は新字体が普及した戦後の昭和中期以降であり、しかも中身は横書きである可能性がとても高いと言える。
さて、ここからはこれら『善逸伝』読み解きの鍵に、私見を交えて、その成立背景を推測していきたい。
生き残った善逸翁
第二次世界大戦が終わると、善逸翁は50に近づく年頃になっていたと思われる。少年期にかなり目立っていた金髪も、そろそろ銀髪になりかわっていたかもしれない。あるいは「鬼畜米英」を謳う当時の日本の風潮を受けて摩擦を避けるべく、黒く染めていたかもしれない。
東京大空襲、原爆投下という恐怖が過ぎ、新しい社会の到来に接したことだろう。善逸翁は、あの無惨も原子爆弾なら一発で倒せただろうなと思ったかもしれない。戦後の日本人が鬼以上の空想生物が暴威を振るう映画『ゴジラ』を見て、こんな化け物を娯楽として享受するほど、今は平和になったのだなと感慨深く思ったかもしれない。年月は進んでいく。
身の回りの人たちも老いた。もと隊士の中には、戦争で行方不明と化した者もいただろう。善逸翁が鬼と戦った事実は、やがて亡失されていく運命にあった。しかし鬼は平安時代の日本で生み出された。人間は原子爆弾すら作り出した。医学の発展も凄まじい。いつかどこかで誰かが人工的に「鬼」を開発して、無惨の同類がまた世界のどこかへ現れてくるかもしれない。
自身の老化、時代の変わりよう、伴侶と子孫の将来など、善逸翁が過去を語り残したくなる環境が満ちていた。そこで彼は自らの息子にすべてを告白することにしたのだろう。ただし善逸は、真実が世間に公開されないで済むことを願っていただろうから、きっと架空の物語であるかのように語ったことだろう。
時期的にその息子は大学生ぐらいだったろう。この時代の大学生は、物事を横書きで筆記する習慣が身に付いている。彼は父が熱心に言い聞かせてくる物語を、はじめは半ば孝行顔、半ば呆れ顔で書き留めただろう。それは、善逸翁の伝記ではなく、無惨退治の物語として完結する予定であった。
父の熱心な語りには強く魅せられたであろう。あまりにも真に迫る内容であったので、これを無惨退治の物語として終わらせるのは惜しいと考えたのではないか。
大学ノートに書かれた『善逸伝』
かくして息子は善逸翁の口伝物語を筆記する。ちらしの裏に書くわけにはいかず、さりとて公的な出版をする予定もないので、原稿用紙も使わない。そこで大学ノートが使われた可能性が高いだろう。
ところで善逸翁には、表現の才能がある。
京極屋で三味線を弾いたとき、「うまいわね」「すごい迫力」「あの子はのし上がるね」等と高い評価を集めた。他人の技術を猿真似するのではなく、自らの内面に消化して表出できる稀有な感性の持ち主だった。
息子は父の物語が世間通用の幻想小説より奇々怪々で、壮絶であることに驚く。古いノートがすべて埋まると、新しいノートを取り出す。こうして何冊もの大学ノートが物語を紡いでいった。「最後の鬼」が退治されたあと、息子は詳細を尋ねたであろう。聞きたいこと、知りたいことが無数に生じていたはずだ
『善逸伝』の後半は、これら質疑応答と脚注で占められた。こうしてこのテキストは、鬼退治の物語というより、善逸個人に関心を向ける伝記としての性格が強くなった。
善逸翁の物語が終わると、息子はこれをひとつにまとめて保管することにした。内容が古典の伝奇小説を想起させるので、和綴の装幀が望ましいと考えたのだろう。燈子は同書を「ひいおじいちゃんの嘘小説」と呼んでいるが、「ひいおじいちゃんが書いた嘘小説」ではなく、「ひいおじいちゃん(善逸翁)を主人公にした嘘小説」という意味だろう。善逸翁から話を聞き終えた息子(燈子と善照の祖父)は、大学ノートの束に穴を開けて紐を通し、一冊の和綴本とした。そして最後に『善逸伝』の外題を付けて、仕事を終えたと思われる。
同書を読み終えた善照少年は、これがきっかけで日本史に興味を持ち、大河ドラマ『麒麟がくる』を見て、「あっ、自分と同じ名前の公方(足利義輝)様が出てる! 斬った! 殺された!」等と興奮しているかもしれない。拙著『平将門と天慶の乱』を読んで、「最初の鬼が生まれた時代は地獄だぜ」と笑ってくれているかもしれない。名作から広がる想像は、どこまでも尽きることがない。
歴史家が紐解く「鬼滅の刃」の世界 一覧
(1)鬼滅の刃・我妻善逸の伝記『善逸伝』を書いたのは?(無料・7月18日公開)
(2)『鬼滅の刃』鬼殺隊が政府非公認になったのはいつ?(7月18日公開)
(3)漫画の王道を覆す『鬼滅の刃』下弦の鬼を完全粛清した無惨の真意(7月19日公開)
(4)『鬼滅の刃』十二鬼月の名前に秘められた、鬼舞辻無惨の真意(7月19日公開)
(5)鬼舞辻無惨の誕生秘話を探る(7月20日公開)
(6)『鬼滅の刃』禰豆子の「血鬼術」が示す、無惨の異能の謎と千年王国(7月20日公開)
(7)【書き下ろし】珠世、四百年の孤独──ある女医の個人史探究(7月21日公開)
※本書は2020年12月4日~2022年12月5日、JBpressに掲載した記事を加筆修正、書き下ろしを加えたものです。
ご購入いただくと過去記事含むすべてのコンテンツがご覧になれます。

過去のコンテンツも全て閲覧可能な月額サブスクリプションサービスです。
🔰シンクロナスの楽しみ方
・「戦国最弱」と言われた武将・小田氏治の真実(現在連載中)
+
・「上杉謙信」「ジャンヌ・ダルク」「戦国時代のリアル」などを題材にした電子書籍や完結連載全6タイトル
・動画&音声「歴史対談」「歴史解説」

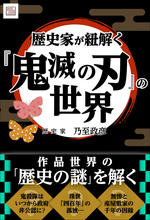
この夏、映画も公開する『鬼滅の刃』。人気漫画や映画の考察に定評のある歴史家が、作品世界の「歴史の謎」に挑む。歴史家ならではの独自の視点で考察で、壮大な物語世界の新たな魅力を見つけよう。
会員登録がまだの方は会員登録後に商品をご購入ください。