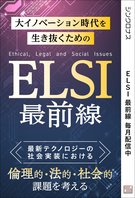服を選ぶとき、それがどこで、どう作られたのか──その背景まで意識したことはあるだろうか。近年、「サステナビリティ」や「エシカル消費」などのキーワードへの関心が高まるなか、リサイクル素材を使った衣服や古着回収ボックスを見かける機会も増えてきた。こうした動きは「よいこと」として広がりつつあるが、その言葉の中身について、立ち止まって考えたことがあるだろうか?
最先端技術に関する倫理的・法的・社会的課題──「ELSI(エルシー)」の考え方をひも解き、社会とビジネスにおける実践的な視点を提供する連載「ELSI最前線」。今月は、様々なものごとを取り巻く価値(観)に関する諸問題を研究する井出和希氏が、ファッションを切り口に、消費者・事業者双方に関わるELSIを読み解く。(第1回/全3回)
💡この記事のポイント
- ファッション産業では、大量の水の消費や汚染、マイクロプラスチックの流出をはじめ、未使用品を含む繊維製品の大量廃棄など、さまざまな環境負荷が指摘されてきた。
- 私たちの身の回りには「サステナブル」な製品や取り組みが溢れているが、果たしてどのくらい本当に持続可能なビジネスモデルを持っているだろうか?
- 「サステナブル」「エシカル」「持続可能な」といった言葉がどのように使われているか、実は明確ではない。
🖊️技術と人のイノベーションをめぐる、専門家との議論に参加しましょう!


大阪大学 CiDER/ELSIセンター 特任准教授。薬剤師、修士(芸術)、博士(薬科学)。静岡県立大学、京都大学を経て現職。疫学、公衆衛生学や健康情報学を基盤に2016年から健康・医療情報の利活用にまつわるプロジェクトで(急に)ELSI担当として関連領域に取り組むようになった。以降、様々なものごと(学術情報流通、先端的な科学技術、ファッション、芸術など)を対象に活動を展開している。プロフィール詳細
服を選ぶ前に考えたい、私たちが日々身にまとう「ELSI」
私たちは日々衣服を身にまとっている。そして、靴やバッグをはじめ、ファッションに関連した多くの製品と生活を共にしている。皆さんはどのような理由でそれらを選択しているだろうか。あるいは、製品を市場に投入する側になるとしたら、どのような理由で選択されることを意図するだろうか。
流行や手頃さもあれば、生産・製造背景、製品やブランドのもつ物語、ヘリテージといった要素も挙がるだろう。そして、その時、生産・製造から最終的に廃棄されるまでの全体像は思い浮かぶだろうか。
それらと切り離すことできない「ELSI(倫理的・法的・社会的課題)」に目を向けてみよう。
とはいえ、本稿の目的は強く消費の抑制を意識させることではない。産業のあり様や国内外の動向に触れながら、どのような要素にどのような意識を向けることができそうかといった提案を通して、消費者が/としてファッションを楽しみつつ——無理なく、長期的に——思考を巡らせることが日々の実践にどのような変化をもたらすだろうか、という問いかけである。
これは、(ファッションに限らず、読者の方々にとって身近な)ビジネスのあり方を再考することにも繋がるかもしれない。
年間9,200万トンの廃棄──見えにくいファッションの環境負荷
ファッションにまつわる「ELSI」は、製品のライフサイクルとの関わりが深く、アセスメントの重要性(とその不十分さ)も指摘されている。
例えば、綿花のような素材の生産*をはじめ店頭に並ぶ製品に至るまでには多くの水が必要であり、環境負荷の高さは1960年代から指摘されている。
*1キロあたり20,000リットルの水を要するとされる(Bhandari N et al., 2022)。しかしながら、たとえ環境負荷が高くとも肌への刺激(負荷)が少なく、筆者のようなアトピー性皮膚炎の患者にはありがたい素材である。一つの側面からよしあしを判断することはできない。
なかなか想像は困難であるが、ファッション産業は2017年時点で年間79兆トンの水を消費しており、2030年には118兆トンに達するとの試算(Pulse of Fashion Industry 2017)*もある。加えて、繊維製品の処理過程や染色を介した汚染、マイクロプラスチックの流出も課題となっている。
それだけでなく、2025年2月に公開された国際連合環境計画(UN Environment Programme, UNEP)のレポート(テクニカル・ハイライト)によると、年間9,200万トンもの繊維製品が廃棄されているとのことだ。これには、ブランドの価値が下がることへの懸念から、未使用の製品も廃棄されてしまう慣習が影響している。
*試算を超え、UNEPのレポートでは既に215兆トンに達していると記されている。
環境によさそうで「サステナブル」な製品は本当に持続可能か?
とはいえ、私たちの身の周りには環境によさそうで持続可能性(サステナビリティ)を高めそうな——私たちの倫理に適う?——製品や取り組みが溢れている。ユニクロをはじめとした衣料品店には不要になった製品を回収するためのボックスがあり、パタゴニアのような思想的にサステナブルなブランドもすぐに思い浮かぶかもしれない。
それらは、ほんとうに「消費され/させつづける」ビジネスモデルを乗り越える何かをもっているだろうか。あるいは、乗り越えるかどうかのゼロイチではないなかで、「どの程度」乗り越えようとしているといえるだろうか。
それはそうと、ELSIの射程が環境に留まるものかどうかにも目を向けてみよう。倫理的であることや持続可能な営みを想起させる「エシカルファッション」や「サステナブルファッション」といった言葉からその要素を眺めてみよう。
エシカル/サステナブルとは結局どういう意味なのか?
具体的な要素を取り上げる前に言葉の曖昧さに言及しておかねばならない。すなわち、エシカル、サステナブル、倫理的な、持続可能なといった言葉がどのように理解され、社会のなかで使われているのかは明確ではないのだ。
Ethical、Sustainableと英語で表記されれば、それらの単語だけがもつ含意もあるだろう。もしこれらの言葉をみかけたら、その言葉が内包する具体的な意味に一歩踏み込んで考えを巡らせ、文脈を読み解いてみてほしい。これは、無数に存在する認証制度(例えば、商品タグ等に印刷された「オーガニックコットン」等のマーク)についても同様である*。
*その一部は、グリーンウォッシング(greenwashing;1987年頃から用いられるようになった言葉で、根拠がなかったり、誤解を招いたりする環境保護主義的なイメージをつくり上げたり広げたりすること(Oxford English Dictionary(OED)による))やエシックスウォッシング(ethics washing)、サステナブルウォッシング(sustainable washing)と批判されることもある。なお、ファッションに限定したものではないが、「greenwashing」という語がオンラインニュース等で用いられる頻度は、2020年から2024年にかけて100万単語あたり0.21から0.45と2倍以上に増えている(同OEDのコーパス(200億単語を含むとされる)に基づく)。
ご購入いただくと過去記事含むすべてのコンテンツがご覧になれます。
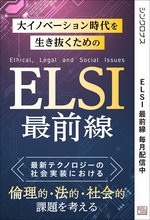
過去のコンテンツも全て閲覧可能な月額サブスクリプションサービスです。
🔰シンクロナスの楽しみ方
イノベーション時代のビジネスに欠かせないリテラシー「ELSI」を身につける、双方向プラットフォーム。専門家とのフラットな議論を通じて、未来を見据えた多角的な判断軸を手に入れよう。
- 記事連載:最新技術や制度の事例をもとに、ELSIの論点を専門家が解説
- フォーラム:読者の疑問や意見に専門家が応答し、議論を深める対話の場
- ニュースレター:注目ニュースや読者の声を、専門家のコメントとともに配信

服を選ぶとき、それがどこで、どう作られたのか──その背景まで意識したことはあるだろうか。様々なものごとを取り巻く価値(観)に関する諸問題を研究する井出和希氏が、ファッションを切り口に、消費者・事業者双方に関わるELSIを読み解く。(全3回)
※本コンテンツは、月額サブスクリプション『ELSI最前線』でも閲覧できます。
会員登録がまだの方は会員登録後に商品をご購入ください。