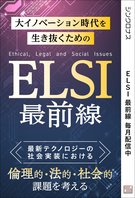「自衛隊が、電磁波で錆を防ぐと謳う謎の装置を導入しかけていた」「香川県が配布した教育教材に、根拠の乏しい“脳科学”が使われていた」——。
こうした怪しげな「疑似科学」が、行政や教育現場を通じて私たちの社会に静かに入り込み、税金や公共の信頼を蝕んでいる。SNSで注目を集めたこれらの事例も、氷山の一角にすぎない。今この瞬間も私たちの生活のすぐそばで、おかしな技術や理論が、まるで当然のように採用されつつあるかもしれない。
最先端技術に関する倫理的・法的・社会的課題──「ELSI(エルシー)」の考え方をひも解き、社会とビジネスにおける実践的な視点を提供する連載「ELSI最前線」。今月は、倫理学を専門とする長門裕介氏が、私たちの日常の中に巧妙に入り込む「地味な疑似科学」を考える。(第1回/全3回)
💡この記事のポイント
- 科学的根拠に乏しい「疑似科学」が、行政や教育現場に「地味で巧妙」な仕方で入り込んでおり、そこには根深い構造的な課題が潜んでいる。
- 問題が指摘されて批判されても、疑似科学を取り入れようとした公的機関は責任を回避し、問題を先送りにする傾向がある。
- 疑似科学への批判は重要だが、見過ごされたり、批判を受けても復活したりすることもある。より効果的で建設的に向き合うにはどうすればよいのか?
🖊️技術と人のイノベーションをめぐる、専門家との議論に参加しましょう!


大阪大学社会技術共創研究センター講師。専門は倫理学、特に幸福論や人生の意味、先端科学技術のELSI(Ethical, Legal and Social Issues 倫理的・法的・社会的課題)。最近の業績に”Addressing trade-offs in co-designing principles for ethical AI”, AI and Ethics, vol.4-2, (A. Katiraiとの共著、2024)、R.ハルワニ『愛・セックス・結婚の哲学』(共訳、名古屋大学出版会, 2024)など。
プロフィール詳細
行政や教育現場に入り込む、地味で巧妙な「疑似科学」
「UFOの技術で反重力エンジンを開発」
「アインシュタインの相対性理論は間違っていた」
「植物と会話できる装置を発明」
——こうした話を聞いたら多くの人は「ほんまかいな」と眉をひそめるだろう。
科学のような装いをしているが実際は科学とは見なされないようなものは「疑似科学」と呼ばれる。前述したような派手な疑似科学ではなく、もっと地味で巧妙な仕方で、私たちの日常に入り込んできている疑似科学があるとしたら、どうだろうか。
2024年1月、陸上自衛隊が「核磁気共鳴で水道管の錆を防ぐ」装置の導入を検討していることが発覚し、科学者らの指摘で入札が中止された。
大阪府泉大津市では市長が「水と空気から軽油ができた」とSNSで発表し、物議を醸した。
香川県では「ゲーム依存で脳が変化する」との学習シートが配布され続け、関連する分野を扱った学会から科学的誤りを指摘されても削除に3年を要した。
なぜこうした怪しげな技術や情報が行政や教育現場に「ぬるっと」入り込んでしまうのか。問題は単なる科学的誤りだけではない。そこには、意思決定のプロセス、情報リテラシー、そして社会的な信頼に関わる、より根深い構造的な課題が潜む。それは、無駄な公費支出だけでなく、行政や教育への信頼を揺るがし、社会全体の合理的な判断力を損なう可能性をはらんでいる。
この疑似科学の問題を、ELSI(倫理・法・社会的課題)の一部として考えてみたい。
自衛隊が入札を取り下げた「電磁波で赤錆を防ぐ装置」
まず、いくつかの事例を紹介しよう。
2024年1月、陸上自衛隊練馬駐屯地が「核磁気共鳴技術により配管内の赤錆を防止する」装置の調達を公告していたことが発覚し、SNSを中心にちょっとした話題になった。
この公告では「電磁波により水の性質を変化させ、赤錆を黒錆に変換する」と称する製品を入札の基準としていた。効果に疑問を呈する報道を受けて、駐屯地は「改めて情報収集を行う必要がある」と判断し、入札公告を取り消した。
その後、自民党の山本朋広議員(当時)は4月17日の衆院内閣委員会でこの問題を取り上げ、「ちまたで疑似科学とかとんでも科学だとか指摘されている」と訴え、同種の装置が自衛隊のいくつかの駐屯地で既に導入済みであること、外務省でも米英とモンゴルの日本大使館に試験的に設置し、国土交通省も国土交通大学校に設置していたことを明らかにした。
しかし、この件について答弁を求められた各省とも「導入の経緯は確認できず、装置の効果を検証していない」とし、「効果の有無はよく分からない」「検証する立場にない」としている。
※陸自駐屯地が入札撤回…自民・山本氏が経緯ただす「とんでも科学だと指摘」(神奈川新聞,2024年4月17日)https://www.kanaloco.jp/news/government/article-1071561.html
市長がSNSに投稿「水と空気から軽油ができる」?
また、2025年7月、大阪府泉大津市の南出賢一市長がX(旧Twitter)で「水と空気から光の力で、45分間で約20リットルの軽油ができました」と投稿し、大きな注目を集めた。
本来無色透明であるはずの軽油が流通過程で着色されたものと同じ緑色をしていたことや、生成に理論上必要な炭素や電力がどう賄われているか不明であることを指摘するコミュニティノートがつくなど、批判にさらされたのである。
実証実験を行った仙台市の企業は、合成燃料ができる仕組みについて「特許出願中」を理由に詳細な説明を避けている。この企業は2023年にも大阪市や大阪府で同様の実証実験を行っていたが、行政側は「実験の成果について把握していない」と回答している。
実証実験を許可する際の科学的妥当性の検討プロセスが不透明で、成果の検証体制も整っていない状況が明らかになった。
※「水と空気から軽油」大阪・泉大津市長の投稿が物議 実証主体企業は特許理由に説明避ける(産経新聞,2025年7月11日)https://www.sankei.com/article/20250711-C5JA5YPDVFDSLMYO6RVVAJCBN4/
※「何か騙されてないか?」 大阪・泉大津市長の“夢の燃料”X投稿に疑問を呈する声が相次ぐ 市の見解は?(ITmedia News,2025年07月11日)https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2507/11/news101.html
「ゲーム依存が脳を変化させる」? 問題ある学習教材を県が配布
次に、教育現場における脳科学の濫用に注目したい。
2020年に全国で初めて香川県で施行された通称「ゲーム条例」はそれ自体かなり物議をかもしたが、その後の教育現場で配られた学習用シートにも問題が指摘されている。
県教育委員会は条例に基づき、児童・生徒向け「ネット・ゲーム依存予防対策学習シート」を配布していたが、この中に「ネット・ゲームの使いすぎによる脳への影響」として、「ゲームに依存している人の脳では、感情や思考を司る部分が変化してしまっている」との説明と脳の画像が掲載されていた。
これに対して、2023年に日本行動嗜癖学会は「医学的・科学的な誤りがある」として県教委に公開質問状を提出した。
問題となった脳画像の引用元論文は、ゲームを長時間プレイしている群と対照群(比較対象となる一般的なグループ)で脳の体積を比較した研究であり、「ゲームプレイが脳の変化の原因である」ということを述べたものではなかった。つまり、学習シートは研究結果の一部を抜き出して元の論文が直接言っていないことを断定的に述べてしまったのである。
しかし県教委は専門学会からの質問状に直接回答せず、報道の質問に対し「一つの見識だと思う」としたうえで「(脳への影響という)伝え方を残した方がいいというのが今年の判断」と述べ、問題の図は2024年度版でも残り続けた。
2025年版では削除されているものの、5年間にわたって科学的に問題のある内容が教材として使われ続けたことになる。
※【解説】ネット・ゲーム依存対策の学習シート 誤り指摘…どう変わった? 香川(KSB瀬戸内海放送NEWS,2024年8月7日)https://news.ksb.co.jp/article/15379474
※香川県・ネット・ゲーム依存予防対策学習シートに関する公開質問状(日本行動嗜癖学会,2023年8月1日)https://jssba.org/?p=1651
誰も責任を取らず、問題は先送りに……
このように、科学的な妥当性が疑問視される技術や正確性を欠いた説明が、行政や教育の現場でまかり通ってしまっていることが、税金の無駄使いや市民の科学的態度への悪影響を招くことは言うまでもない。
しかし、私がここで注目したいのは、こうした疑似科学的な内容を取り入れようとした公的機関が批判を受けた際の対応の仕方である。
「導入の経緯は確認できず、装置の効果を検証していない」
「場所を提供しただけで、成果の報告などは求めていない」
「(批判に対して)そういう受け止め方もある」
「毎年より良いものになっていくように考えていく」
——いずれも、疑似科学そのものを推進したわけではないという姿勢を示しつつ、責任の所在を曖昧にし、問題を先送りする対応が共通している。追及を受けて「なぜこの程度のことが問題にされるのか」と考える担当者がいても不思議ではない。
私が、冒頭で疑似科学が「ぬるっと」日常に入り込んでいるとしたのはまさにこうした状況を指している。
日常に入り込む「疑似科学」、どう向き合うべき?
「問題となるような気候変動は存在しない」「コロナはただの風邪である」といった極端な発言はよく目につき、批判されやすい。アメリカでは「地球は平面である」「聖書の天地創造の通りに地球や生物は創造された」と心から信じている人が少なくない、と聞けば日本に住む多くの人の目には滑稽に映るだろう。
※三井誠 (2019)『ルポ 人は科学が苦手 アメリカ「科学不信」の現場から』光文社新書
近年、無視できない程度に存在感が増してきたとはいえ、日本では科学的根拠の乏しい主張が政策に大きく影響することについて、多くの市民が一定の距離感を保っており、アメリカほど深刻な状況ではない、という意見もあるかもしれない。
しかし、行政機関の設備調達や後援事業、教育委員会の作成したワークシートといった非常に地味なレベルでは着々と疑似科学が入り込んでいるのだ。
今回紹介した事例では、追及を行った科学者、専門家、記者、議員といった人々は、重要な役割を果たしたと言える。ただし、見過ごされているものは他にもあるだろうし、批判を受けても何度でも復活してしまう疑似科学もある。また、疑似科学を批判することは当人にとって益が少ない行為であるし、批判のやり方も問題の深刻さに応じて工夫が必要だ。
では、どうすればより効果的で建設的な仕方で疑似科学と向き合っていくことができるだろうか。
【次回は8月13日(水)更新予定】科学者が疑似科学を批判できないのはなぜ?
🖊️あなたの視点をお聞かせください(別ウィンドウで開く)
ご購入いただくと過去記事含むすべてのコンテンツがご覧になれます。
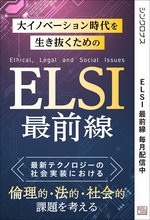
過去のコンテンツも全て閲覧可能な月額サブスクリプションサービスです。
🔰シンクロナスの楽しみ方
イノベーション時代のビジネスに欠かせないリテラシー「ELSI」を身につける、双方向プラットフォーム。専門家とのフラットな議論を通じて、未来を見据えた多角的な判断軸を手に入れよう。
- 記事連載:最新技術や制度の事例をもとに、ELSIの論点を専門家が解説
- フォーラム:読者の疑問や意見に専門家が応答し、議論を深める対話の場
- ニュースレター:注目ニュースや読者の声を、専門家のコメントとともに配信

怪しげな「疑似科学」が、行政や教育現場を通じて私たちの社会に静かに入り込み、税金や公共の信頼を蝕んでいる。倫理学を専門とする長門裕介氏が、私たちの日常の中に巧妙に入り込む「地味な疑似科学」を考える。(全3回)
※本コンテンツは、月額サブスクリプション『ELSI最前線』でも閲覧できます。
会員登録がまだの方は会員登録後に商品をご購入ください。