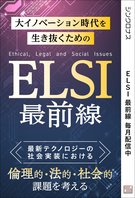センサー付き首輪やAI搭載アプリで、愛犬・愛猫の気持ちが理解できるようになった! しかし、そこに表示される「動物の気持ち」が、実は人間にとって都合がいい解釈の押し付けだったら……?
近年、AIやセンサー技術を使って、犬や猫といったペットや牛・豚などの畜産動物の感情を理解するための技術が発展し、実際の製品やサービスにも応用され始めている。一方で、誤判定のリスク、動物福祉や制度設計に関する懸念などの課題も残されている。
最先端技術に関する倫理的・法的・社会的課題──「ELSI(エルシー)」の考え方をひも解き、社会とビジネスにおける実践的な視点を提供する連載「ELSI最前線」。今月は、哲学・概念工学を専門とする鹿野祐介氏が、動物の感情推定技術の現在地、さらには「動物の感情を理解するとはどういうことか?」といった根源的な問いを考える。(第2回/全4回)
💡この記事のポイント
- 動物の感情を推定するAI技術は、ペットだけでなく家畜にも応用され、管理効率の向上と動物福祉の両立が目指されている。
- こうした技術には、「牛のFitbit」と呼ばれる首輪型デバイスなど、実用化段階に入っているものもある。
- 実際には人間にとっての効率を高める手段として導入され、「動物福祉の向上」が方便として利用される構図がある。
🖊️技術と人のイノベーションをめぐる、専門家との議論に参加しましょう!


大阪大学COデザインセンター特任講師。東北大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。同大学社会技術共創研究センター(ELSIセンター)を兼担。専門は哲学/概念工学。ELSIセンターでは、責任ある研究開発に関する実践研究とELSI人材の育成開発に取り組んでいる。共編著に『ELSI入門』(丸善出版, 2025)、訳書に『デジタルテクノロジーと時間哲学』(丸善出版, 2024)などがある。 >>プロフィール詳細
畜産業でも活用を目指す、動物の気持ちを理解する技術
動物の感情を推定する技術は、ペットだけでなく、私たちの食生活を支える牛や豚、鶏といった家畜にも応用され始めている。
畜産の現場では、飼育環境の快適さやストレスの有無が生産性や品質に直結する。
もし、「この環境は心地よい」、「この状況はストレスを多く感じる」といった動物の感情や感覚を正確に知ることができれば、事故や病気を予防し、肉や乳製品の安定供給につなげることもできるかもしれない。
鳴き声の解析を通じた感情の分類モデル
...