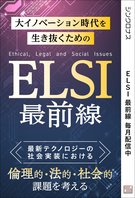服を選ぶとき、それがどこで、どう作られたのか──その背景まで意識したことはあるだろうか。近年、「サステナビリティ」や「エシカル消費」などのキーワードへの関心が高まるなか、リサイクル素材を使った衣服や古着回収ボックスを見かける機会も増えてきた。こうした動きは「よいこと」として広がりつつあるが、その言葉の中身について、立ち止まって考えたことがあるだろうか?
最先端技術に関する倫理的・法的・社会的課題──「ELSI(エルシー)」の考え方をひも解き、社会とビジネスにおける実践的な視点を提供する連載「ELSI最前線」。今月は、様々なものごとを取り巻く価値(観)に関する諸問題を研究する井出和希氏が、ファッションを切り口に、消費者・事業者双方に関わるELSIを読み解く。(第2回/全3回)
💡この記事のポイント
- 「サステナブルファッション」の要素を整理すると、課題は環境にまつわるものだけではないということがわかる。
- Dior(ディオール)の労働搾取疑惑や、SHEIN(シーイン)の児童労働問題など、労働の問題を避けることはできない。
- 合成皮革が「ヴィーガンレザー」と呼ばれたり、天然皮革が「エコレザー」と呼ばれたりするなど、混乱を招きかねない表現にも気を付けたい。
- 反消費・反生産の観点から、Bottega Veneta(ボッテガ・ヴェネタ)の無料の修理サービスなどが話題になったが、ビジネスを成立させるためには消費し続けてもらわねばならないというジレンマもある。
🖊️技術と人のイノベーションをめぐる、専門家との議論に参加しましょう!


大阪大学 CiDER/ELSIセンター 特任准教授。薬剤師、修士(芸術)、博士(薬科学)。静岡県立大学、京都大学を経て現職。疫学、公衆衛生学や健康情報学を基盤に2016年から健康・医療情報の利活用にまつわるプロジェクトで(急に)ELSI担当として関連領域に取り組むようになった。以降、様々なものごと(学術情報流通、先端的な科学技術、ファッション、芸術など)を対象に活動を展開している。プロフィール詳細
「サステナブルファッション」とは一体何を指すのか?
第1回で論じた前提のもと、包括的な概念としてのサステナブルファッション(sustainable fashion)が研究上どのような概念を含むのかについてみてみよう。
Mukendi Aらの総説(対象は、2000年~2019年6月に出版された465報の論文)によると、これらに限定される訳ではないという留保のもと、以下の要素に整理された(Mukendi A et al., 2020; 順序は本稿の構成に応じて筆者調整)。
A) 環境(的)
B) 社会(的)
C) クルーエルティフリー(動物を傷つけたり殺したりしないこと)
D) 反消費・反生産の実践
E) スローファッション
F) リユース
G) リサイクル
要素として違和感はないが、これらを全て考慮した製品というのはあり得るのだろうか。一つでも考慮していればよいのか、何をどの程度順守することで——法の範疇に留まらず、社会のなかで——許容されるのか(あるいは、順守されていなかったとしても許容されるのか)という点には議論の余地がある。加えて、社会の側のまなざしが更新され続けるものであることには留意したい。
それでもここで要素を列挙した理由は、課題が環境にまつわるものだけではないことに想像を広げるためである。そして、これらの要素・観点についてもう少し詳しくみていきたい*。
*サステナブルファッションの倫理的な原則については、Niinimäki K(2015)の総説も参考になろう。
ファッション産業の社会問題——後を絶たない労働搾取疑惑
社会(的)な観点では、労働の問題を避けることはできない。...