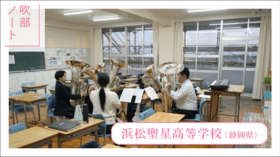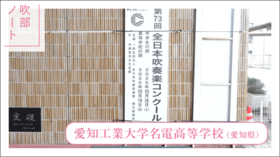吹奏楽部員たちが部活に燃える日々の中で、書き綴るノートやメモ、手紙、寄せ書き……それらの「言葉」をキーにした、吹奏楽コンクールに青春をかけたリアルストーリー。ひたむきな高校生の成長を追いかける。
第47回は愛知工業大学名電高等学校(愛知県)#6(#1はこちらからご覧になれます)。
本連載をもとにしたオザワ部長の新刊『吹部ノート 12分間の青春』(発行:(株)日本ビジネスプレス 発売:ワニブックス)が好評発売中。
吹奏楽部員、吹奏楽部OB、部活で大会を目指している人、かつて部活に夢中になっていた人、いまなにかを頑張っている人に読んで欲しい。感涙必至です!
彼女たちの涙
15校の演奏がすべて終わり、残すは表彰式だけになった。
名電からは代表としてナギサとミサキ、そして、宏樹先生がステージに出ることになっていた。
他校の代表者とともに舞台袖で待機しているとき、ナギサはミサキに言った。
「すべてやりきったんだし、どんな結果でもいいよね」
さすがのナギサもそのときは胸が高鳴っていた。まわりには強豪校、有名校が集まっている。その場に自分もいられることがなんだか嬉しかった。
表彰式が始まり、代表者はステージのひな壇に並んだ。客席ではユイカやホノカ、ルリ、部員たちが祈るようにステージを見つめていた。
プログラム順に1番から次々と審査結果が発表されていく。「ゴールド金賞」という声が響くと、キャーッと歓声が上がった。
いよいよ名電の番が近づき、壇上の3人はステージの中央に進んでいった。
「13番、愛知工業大学名電高等学校——」
誰もが固唾を呑んでその続きを待った。
「銀賞」
歓声はなく、拍手が響く中でナギサは表彰状を、ミサキはトロフィーを、先生は指揮者賞の記念品を受け取った。
(どんな結果でもいいって自分で言ったけど、大好きな仲間たちと一緒に後悔のない楽しい演奏ができたし、やっぱりいい賞が欲しかったな。銀か……)
ナギサはそう思わずにはいられなかった。
表彰式が終わり、代表者は舞台袖に下がった。ふと、宏樹先生が言った。
「いけたと思った」
金賞に手が届いたと先生は感じていたのだ。名電は決してコンクールで良い賞をとることを目標にはしていない。誰よりも、それを大事にしているのは宏樹先生だ。しかし、それでも今年は特別にいい演奏ができたと思ったからこそ、先生は「いけた」と感じたのだろう。
その言葉を聞き、ナギサとミサキは泣いた。
先生もそう思っていてくれたのだ。だとしたら、なおさら悔しかった。
客席にいる部員たちの中にも涙を流す者もいた。
その様子を見ながら、ユイカは今年も泣けなかった。でも、それは本気になれていなかったからではなかった。自分は人前で自然と感情をセーブしてしまうタイプだということにユイカは気づいていた。それに、副部長として、みんなのケアもしなければいけない。
同じように、ホノカも泣いていなかった。悲しい気持ちもあったが、それよりも楽しい演奏ができたという実感が勝っていた。会場に来たときと同様、実務も残っている。みんなをホールから連れ出し、バスに乗せ、東京駅で新幹線に乗り換えさせ、名古屋まで無事に帰り着かなければならない。
「泣いてる暇なんてない!」とホノカは自らを鼓舞した。
ナギサやミサキがステージに行っている以上、残された副部長3人がしっかりしなければいけない。
ルリは審査結果を聞き、近くにいた姉と顔を見合わせた。
「あんなによかったのにね」
姉はぽつりと言った。
自分もそう思った。あの演奏に銀賞という結果がついて、心にぽっかり穴が空いたような気持ちになった。
(楽しかったのに、それだけじゃダメだったのかな……)
心の穴の奥から悔しい思いが湧き出てきた。ただ、姉と同じ気持ちを共有できることがルリにとっては救いだった。
メンバーはバスに乗って会場を出ると、東京駅を目指した。途中、サービスエリアに立ち寄るまで、車内では沈黙が続いていた。しかし、そこで弁当を食べるとみんな元気を取り戻し、いつもの賑やかさが戻ってきた。
東京駅に着き、新幹線に乗り換える途中で、ホノカはこんな声を耳にした
「このメンバーでやれてよかったね」
ホノカ自身も同じ思いだった。おそらく、みんなも——。

新幹線で名古屋駅に着き、そこで解散となった。
ルリは、母と姉と一緒に自宅へ帰った。道中ではずっとSNSをチェックし、自分たちの演奏を高く評価してくれている人が多いことを知った。
「やっぱり私たちの演奏は間違ってなかったんだよね」
ルリは姉にそう言った。
それでも、ぽっかり空いた心の穴は塞がらなかった。それは、銀賞だったことではなく、もうコンクールが終わってしまい、二度と戻ってこないからなのだとルリは気づいた。
(ここで区切りをつけないといけないんだよね)
まだこの先に大きな目標、来年1月の定期演奏会がある。それが自分たち3年生にとって、本当の意味で最後の演奏機会だ。おそらく《藍色の谷》も演奏するだろう。
(定期演奏会で今日以上の《藍色の谷》が演奏できたら、すっきりした気持ちで引退できるな)
それは、姉のトニックを着る最後のときでもある。そのとき、ルリとマナ、二人分の青春が終わるのだ。
遠征中、ずっと一緒だった名電の55人は、それぞれがひとりの高校生に戻り、それぞれの思いを抱きしめながら眠りについたのだった。
79日後の私たちへ
「日常は、本当にそのまま日常だったんだな」
全国大会の翌日、ユイカはそう感じた。...