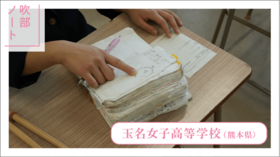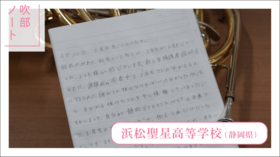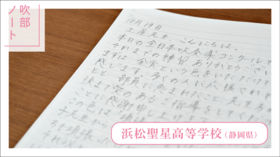吹奏楽部員たちが部活に燃える日々の中で、書き綴るノートやメモ、手紙、寄せ書き……それらの「言葉」をキーにした、吹奏楽コンクールに青春をかけたリアルストーリー。ひたむきな高校生の成長を追いかける。
第45回は愛知工業大学名電高等学校(愛知県)#4(#1はこちらからご覧になれます)。
本連載をもとにしたオザワ部長の新刊『吹部ノート 12分間の青春』(発行:(株)日本ビジネスプレス 発売:ワニブックス)が好評発売中。
吹奏楽部員、吹奏楽部OB、部活で大会を目指している人、かつて部活に夢中になっていた人、いまなにかを頑張っている人に読んで欲しい。感涙必至です!
「パーフェクト」の重圧と孤独を乗り越えた部長、ナギサ。コロナ禍で夢を絶たれた姉の想いを、託されたトニックに込めて戦う副部長、ルリ。だが、213名の愛知工業大学名電高校吹奏楽部を率いる幹部は彼女たちだけではない。ナギサを支え、ルリとともに高みを目指す3人の副部長たち。彼女たちもまた、それぞれの場所で見てきた景色と、譲れない想いを胸に秘めていた——。
2人目の副部長・ミサキ、選ばれし者
(去年の全国大会、帰りのバスの中でナギサとずっとしゃべってたなぁ……)
クラリネット担当の澄川実咲(ミサキ)の脳裏に、部長のナギサとの思い出がよみがえってきた。ちょうど1年前のことだ。
(全力で全国大会の演奏をやりきれたかっていうと、そうじゃない気がする。お互いにそれが悔しかったんだよね。金賞をとった学校が喜んでいるのを間近で見ながら、私たちは銀賞で。もちろん、賞は後からついてくるもの。でも、たとえどんな賞だとしても、全力でやりきって後悔はしたくない。ナギサとはその思いを確認しあったんだ——)
いま、ミサキはナギサを支える副部長のひとりになっている。今年の名電の副部長は4人の3年生。年によって副部長の数は変わる。部員の投票で特別に信頼されていると判断された者が幹部に選ばれるのだ。
ミサキは名電に入る前、「自分の実力では、名電みたいなすごい学校でやっていくのは無理かな」と思っていた。入部した年のコンクールに向けて、55人の座奏A(コンクールメンバー)が発表され、3人の1年生が抜擢されていた。そのうちのひとりがミサキだった。
「ずっと頑張ってきた3年生の先輩もいるのに、まだ右も左もわからない私がなんで……」
嬉しいよりも戸惑った。だが、選ばれたからには本気でやらないと、選ばれなかった先輩たちに失礼だと頭を切り替えた。
ミサキは普段はふわふわした少女だが、楽器を手にすると性格が変わり、ストイックに演奏に没頭する。座奏Aの先輩たちとの力量の差を埋めよう、少しでも吸収しようと必死にクラリネットを奏でた。たっぷり学校で練習をした後も、毎日自宅に帰ってからの個人練習を欠かさなかった。

そんなミサキの悩みは、同期との距離だった。
まだ同期と親しくなっていないうちに、先輩たちに交じってコンクールへの挑戦が始まった。ほかの1年生とは自然と一緒に過ごす時間が少なくなった。「いきなり座奏Aなんてすごいね」と言われるのは嬉しかったが、「自分たちとは違う」と思われているようで寂しかった。
しかも、特進・選抜コースにいたため、部員の多くが所属する普通コースとは教室も離れており、「ミサキちゃんはレアキャラ」と言われるほど顔を合わせる機会も少なかった。
ミサキは同期と話すときはコンクールの話題を極力出さず、教室でも楽譜を開いたりしないようにしていた。「違う」と思われたくなかったのだ。
そんな苦労もあったが、ハイレベルな先輩たちと音楽をつくり上げることには、いままで経験したことがない喜びを感じた。初めて「吹奏楽の甲子園」——全日本吹奏楽コンクールに出場し、自由曲《交響詩「モンタニャールの詩」》を演奏しながら「こんなすごい音楽を奏でられてるんだ!」と感動に震えた。結果は銀賞だったが、演奏には満足していた。
「でも、あの演奏は先輩たちの力でできたもので、私は全然貢献できてなかった……。来年からは自分も名電の音楽を引っ張れる存在になりたい」
ミサキはそう思いながら会場を後にした。
「どソロ」のプレッシャーを越えて
ミサキは高2でも座奏Aに選ばれた。もっと部活に時間を注ぎたいと、特進・選抜コースから普通コースに転身して練習に没頭した。
この年、全国大会では自由曲《ディオニソスの祭り》を演奏したが、ミサキには「全力でやりきることができなかった」という後悔が残った。だからこそ今年、高校最後の年にかける思いは強かった。
春に顧問の伊藤宏樹先生が楽譜を配り、ずっと練習してきたのはオットリーノ・レスピーギ作曲《バレエ音楽「シバの女王ベルキス」》だった。
「最後の自由曲は《ベルキス》になるのなのかな?」
ミサキだけでなく、みんなもそう噂していた。何度か演奏会で披露したが、そのたびに好評だった。
「でも、本当にこの曲でいいのかな……」
決して悪くはない。だが、ほんの少しだけ、しっくりこないものを感じていた。
すると、コンクールの申し込みが間近に迫ったある日、《藍色の谷》の楽譜が配られた。
手にした瞬間、ミサキは凍りついた。曲の冒頭、1小節目に「Solo」の文字があったのだ。しかも、ほかの楽器が演奏していない中、クラリネットの音だけが響く、いわゆる「どソロ」だ。課題曲が終わった後、ピンと張りつめた緊張感の中で、たったひとりで吹かなければならない。もし失敗したら、自由曲全体に大きく影響してしまう。

「できない……」
1年のときから座奏Aだったミサキでも、そのプレッシャーに耐えられそうになかった。
「私、課題曲が終わったら退場するから」
半ば本気でほかのメンバーにそう言っていた。
ところが、楽譜が配られた3日後、ホール練習で《藍色の谷》を演奏したとき、ミサキはみんなの心がざわめいているのがわかった。ほかならぬミサキ自身も興奮していた。
(何カ月も練習した《ベルキス》より、3日目の《藍色の谷》のほうがいい演奏になってる! この曲で頑張りたい!)
逃げ出したいと感じていた冒頭のソロも、俄然やる気が出てきた。
その後、名電は県大会や東海大会などを経て、全国大会への出場が決まった。
日本中の吹奏楽部員が憧れる「吹奏楽の甲子園」。それが、たとえようもないほどの緊張に襲われる場だということを、ミサキは2年間の経験でよくわかっている。
「たとえプレッシャーを感じても、『これだけ練習してきたんだ』という自信があったら、きっと本番でのびのび演奏できるはず。座奏Aに選ばれている1、2年生の大変さは私もよくわかるから、後輩たちが壁を乗りこえ、3年生と一緒に後悔のない音楽がつくれるようにしたいな」
ミサキはそう思っている。
苦楽をともにしてきたナギサや副部長たち、同期のみんな——。いまこそ名電の「絆」の力を発揮するときなのだ。
3人目の副部長・ユイカの決意
(なんで私は涙が出なかったんだろう……)...