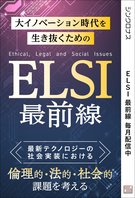センサー付き首輪やAI搭載アプリで、愛犬・愛猫の気持ちが理解できるようになった! しかし、そこに表示される「動物の気持ち」が、実は人間にとって都合がいい解釈の押し付けだったら……?
近年、AIやセンサー技術を使って、犬や猫といったペットや牛・豚などの畜産動物の感情を理解するための技術が発展し、実際の製品やサービスにも応用され始めている。一方で、誤判定のリスク、動物福祉や制度設計に関する懸念などの課題も残されている。
最先端技術に関する倫理的・法的・社会的課題──「ELSI(エルシー)」の考え方をひも解き、社会とビジネスにおける実践的な視点を提供する連載「ELSI最前線」。今月は、哲学・概念工学を専門とする鹿野祐介氏が、動物の感情推定技術の現在地、さらには「動物の感情を理解するとはどういうことか?」といった根源的な問いを考える。(第1回/全4回)
💡この記事のポイント
- AIやセンサー技術の発展により、犬や猫などの動物の感情を推定・可視化する試みが進んでいる。
- 鳴き声や動きを解析する「スマート首輪」や、“猫語”を翻訳するアプリなど、技術が実用化されつつある。一方で、AIの誤判定や擬人化による誤解といった課題も指摘されている。
- テクノロジーによって感情を判定することは、動物を「理解する」ことと言えるのだろうか?
🖊️技術と人のイノベーションをめぐる、専門家との議論に参加しましょう!


大阪大学COデザインセンター特任講師。東北大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。同大学社会技術共創研究センター(ELSIセンター)を兼担。専門は哲学/概念工学。ELSIセンターでは、責任ある研究開発に関する実践研究とELSI人材の育成開発に取り組んでいる。共編著に『ELSI入門』(丸善出版, 2025)、訳書に『デジタルテクノロジーと時間哲学』(丸善出版, 2024)などがある。 >>プロフィール詳細
動物の気持ちを「知りたい」と思う私たち
あなたはペットを飼っているだろうか。
犬や猫と一緒に暮らしている人なら、きっと一度は「この子はいま、どんな気持ちなんだろう」と思ったことがあるはずだ。もし飼ったことがなくても、他の人がペットと散歩をするのを見たり、自慢げにペットの話をするのを耳にしたことはあるだろう。
散歩に出かけるときのはしゃいだ様子や、ご飯をねだるときの真剣なまなざしには、確かに喜びや期待が感じられる。また、病院に連れて行くときの不安そうな仕草や、知らない人に吠えるときの緊張感には、恐れや怒りのような感情が垣間見える。
私たちはその行動や表情を手がかりに彼らの「気持ち」を推し量ろうとするが、実際のところ、その内面の部分を本当に理解できているのかどうかはわからない。
近年、AIやセンサー技術の発達によって、こうした「知りたい」という願いを叶えようとする試みが急速に進んでいる。
犬や猫など、動物の鳴き声や動きを解析して、いま感じている感情を「幸せ」や「不安」といったラベルで表示する装置や、生成AIと連動させて鳴き声を人間の言葉に翻訳する技術まで登場してきた。
動物に対する感情推定技術のELSI
まるでペットと会話できるような未来さえ予感させるような技術だが、同時に気になることもある。
もしAIによって犬や猫が「リラックスしている」と判定したとして、それは本当にその動物自身の気持ちを正しく表しているのだろうか。もしかすると、私たちが信じたい「解釈」をAIが押しつけているだけかもしれない。
動物の感情を推定する技術は、私たちの生活をより豊かに豊かにしてくれる一方で、誤判定や擬人化など新たなリスクも抱えている。そして何より、「動物の感情を理解するとはどういうことか」という根源的な問いを避けて通ることはできない。
ここでは、ペットや家畜となる動物たちを対象にした、動物の気持ちを「理解する」ための感情推定技術の現在地と、その背後にある倫理的・法的・社会的課題(ELSI)について考えてみたい。
「スマート首輪」でペットの状態を可視化する
動物の感情を推定する技術のなかでも、最も身近に感じられるものといえば、ペット向けの製品だろう。
なかでも、スマート首輪(smart collar)と呼ばれる技術は近年注目されている。スマート首輪には、生体情報を収集するセンサーが組み込まれており、収集したデータをAIが解析することで、装着した動物の鳴き声や行動から状態を推定することができる。こうした首輪型デバイスの研究開発は発展を続けており、すでに製品化も始まっている。
たとえば、2021年に韓国のスタートアップ企業ペットパルス(Petpuls Lab)は、犬の鳴き声から感情を判別できるスマート首輪を発表した[1]。
1万件を超える鳴き声データを学習させたAIモデルを搭載し、犬の鳴き声をもとに幸せ・リラックス・不安・怒り・悲しみという5種類の感情に分類する仕組みである。首輪とアプリを連動させると、いま犬がどんな気持ちでいるのかがリアルタイムに表示できるとされ、感情判定の精度は平均して90%とうたわれている[2] [3]。
そのため、たとえば、出勤の前に「不安」の表示が続けば、犬が留守番に対して強いストレスを感じているサインかもしれない。散歩中に「リラックス」と表示されれば、散歩がストレスフリーであることや散歩道が快適であることを知る手がかりになるかもしれない。
飼い主にとっては、言葉を持たないパートナーの状態を可視化する画期的なツールに映るだろう。
翻訳アプリで「猫語」を理解する
首輪型デバイスに加えて、猫の鳴き声そのものを「翻訳」するアプリも開発されている。
その代表例として、米ワシントン州ベルビューのソフトウェア企業Akvelonが手がけたアプリケーションMeowTalk(日本では「にゃんトーク」)がある。
このアプリは、2億6,000万件以上の猫の鳴き声データをもとに、猫の鳴き声を解析し、「お腹がすいた」、「不満」、「警戒」など11種類の意図に翻訳し、スマートフォン上に表示する仕組みである。完全な正確さがあるものではないが、ユーザーが翻訳を修正し、自分の飼い猫特有の語彙やパターンを学習させることで、その猫に合わせて翻訳を調整する仕組みがあり、愛猫との距離を縮めたい飼い主に注目されている。2020年のリリース以来、世界で2,000万回以上ダウンロードされ、これまでに10億件を超える鳴き声が分析されたとされる。
開発者や一部の報道によれば、9種類のフレーズを約90%の精度で分類できたという研究もある。その一方で、たとえば、「I love you(愛してる)」と翻訳された鳴き声が、実際には「新しい餌をちょうだい」だったなど、その精度の不安定さも報告されており、過信のリスクが指摘されている[4] [5]。
これらペットの声を翻訳するツールは、ペットと飼い主の距離を縮める有望なツールであると同時に、その翻訳結果の曖昧さや精度の限界もあり、AIが示す「翻訳」をどう受け止めるかが課題となっている。
それは本当にペットを「理解する」と言えるのか?
こうしたペットの気持ちを「理解する」技術は、飼い主と動物の関係をより親密にし、健康や行動管理の新たな可能性を開くと期待されている。
その反面、いくつかの懸念も浮かび上がってくる。
まず、精度の問題がある。AIが「幸せ」と判定しても、実際は動物がストレスを感じているかもしれない。このような誤判定は、飼い主を安心させる一方で、本来必要なケアを遅らせてしまう危険がある。
また擬人化の問題もある。飼い主は「うちの子が話してくれた」と感じるかもしれないが、それはあくまでAIが過去の厖大な学習データをもとに生成した推測値にすぎず、当の動物自身の意識や感情を正確に映しているとは限らない。
ペットを「理解する」ための望ましい技術だからこそ、センサーで測られた数値やAIによる解釈をどこまで信じてよいのか、また、それは本当にその動物自身を「理解する」と呼べるのかが私たち一人ひとりに突きつけられることになる。
【次回更新は10月22日(水)予定】牛や豚の感情を理解するのは誰のため?
[1] Martin, D., Roberts, D. L., & Bozkurt, A. (2024). Preliminary analysis of collar sensors for guide dog training using convolutional long short-term memory, kernel principal component analysis and multi-sensor data fusion. Animals, 14(23), 3403. https://doi.org/10.3390/ani14233403
[2] Park, M. (2021, January 12). South Korean firm’s smart dog collar tells owners what’s in a bark. Reuters. https://www.reuters.com/lifestyle/oddly-enough/south-korean-firms-smart-dog-collar-tells-owners-whats-bark-2021-01-12/
[3] https://www.petpuls.net/en/petpuls
[4] Suryavanshi, A., Jain, V., Kukreja, V., Choudhary, A., & Chamoli, S. (2023). Feline SentiNet: Deciphering cat discomfort with deep learning and random forest for pain grading. 2023 International Conference on Innovative Computing, Intelligent Communication and Smart Electrical Systems (ICSES) (pp. 1–7). IEEE.
[5] Arnold, C. (2024, October 23). What is your cat telling you? New technology deciphers meows. National Geographic. https://www.nationalgeographic.com/animals/article/cats-pets-communication-app-technology
🖊️あなたの視点をお聞かせください(別ウィンドウで開く)
ご購入いただくと過去記事含むすべてのコンテンツがご覧になれます。
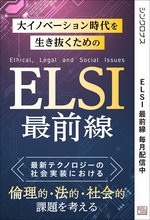
過去のコンテンツも全て閲覧可能な月額サブスクリプションサービスです。
🔰シンクロナスの楽しみ方
イノベーション時代のビジネスに欠かせないリテラシー「ELSI」を身につける、双方向プラットフォーム。専門家とのフラットな議論を通じて、未来を見据えた多角的な判断軸を手に入れよう。
- 記事連載:最新技術や制度の事例をもとに、ELSIの論点を専門家が解説
- フォーラム:読者の疑問や意見に専門家が応答し、議論を深める対話の場
- ニュースレター:注目ニュースや読者の声を、専門家のコメントとともに配信

センサー付き首輪やAI搭載アプリで、愛犬・愛猫の気持ちが理解できるようになった! しかし、そこに表示される「動物の気持ち」が、実は人間にとって都合がいい解釈の押し付けだったら……? 哲学・概念工学を専門とする鹿野祐介氏が、動物の感情推定技術の現在地、さらには「動物の感情を理解するとはどういうことか?」といった根源的な問いを考える。(全4回)
※本コンテンツは、月額サブスクリプション『ELSI最前線』でも閲覧できます。
会員登録がまだの方は会員登録後に商品をご購入ください。