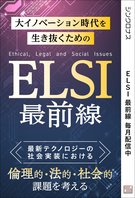わずか数行のテキストから楽曲が生成され、瞬く間に世界中に配信される——。
生成AIの登場によって、音楽の作り方や演奏、そして聴いて楽しむ体験さえも大きく変わろうとしている。その一方で、著作権や文化への影響等、解決すべき課題も山積みだ。AI音楽は、私たちの音楽との関わり方をどのように変えていくのだろうか。
最先端技術に関する倫理的・法的・社会的課題──「ELSI(エルシー)」の考え方をひも解き、社会とビジネスにおける実践的な視点を提供する連載「ELSI最前線」。今月は、音楽学・文化政策学等を専門とし、産学連携の研究にも取り組む肥後楽氏が、音楽生成AIをめぐる新たな問いを考える。(第1回/全3回)
💡この記事のポイント
- 「音楽生成AI」が進化しつつある。例えば、テキストによる説明から1分足らずで楽曲を生成でき、音楽配信サービスにアップロードして収益化も可能。
- 多くのAIは学習データの内訳が不透明で、アーティストやレコード会社の間に権利侵害への不安が広がっている。アメリカではAI制作会社に対する訴訟や学習素材の開示を義務付ける法案提出といった動きもある。
- 一方で、創作において新たな刺激やアイディアをもたらす、音楽の知識や技術がなくても作曲や演奏に参加できる、などのポジティブな側面もある。
🖊️技術と人のイノベーションをめぐる、専門家との議論に参加しましょう!


大阪大学社会技術共創研究センター特任助教。大阪大学大学院文学研究科単位取得退学。専門は、音楽学、文化政策学、協働形成。ELSIセンターでは「芸術とELSI」に関する探索的研究を推進すると共に、異分野を「つなぐ」人材として人社系産学連携の基盤構築をテーマとした研究に取り組む。最近の業績に「テクノロジーと音楽の結びつき―そして音楽生成AIへ」『フィルカル』9(2),(吉村汐七との共著、2024)、「ELSI/RRIをめぐる産学連携:大阪大学社会技術共創研究センターと株式会社メルカリmercariR4Dの事例から」『ELSI入門』第5章(丸善出版, 2025)など。プロフィール詳細
文章・写真だけでなく音楽もAI生成が身近に?
2022年11月にOpenAI社がChatGPTを発表してから、早くも3年が経とうとしている。この間、生成AIは既に私たちの生活に深く浸透したと言って良いだろう。
メール文章の作成、文章の要約などビジネスシーンで活用している人もいれば、アイディアの壁打ち役や知らない事柄のリサーチ、悩み事の相談役や今夜の夕ご飯のレシピの提案など、個人的な問題やプライベートな場面で活用している人もいる。もしくは、自分や家族の写真を「◯◯風のイラストにしてください」と注文し、画像生成を体験した人も多いだろう。
こうしたテキスト生成や画像生成と同様に、音楽の生成についても現在多様なツールが発表され、進化を続けている。今回は音楽生成AIのELSIについて考えてみたい。
そもそも、音楽生成AIとは?
テキスト生成や画像生成と同様、音楽生成AIも様々な企業や研究機関からツールが発表されている。
一口に「音楽を生成する」と言っても、リズムやベースラインなど楽曲全体の一部を出力するものから、ボーカルや歌詞を含めた楽曲全体を生成するもの、さらには入力した音声を異なる音色に変換するタイプの音楽生成AIまで、そのパターンも幅広い。
例えば、日本語のテキストから楽曲を生成することが可能な「Suno AI」で、どうやって音楽を生成するのか見てみよう。
ユーザーは、自分が作りたい曲のイメージをテキストで説明する。どんな気分の時に聴きたい曲なのか、どんなジャンルの音楽なのか。また、出力されるボーカルについて、男声・女声を選ぶことも可能だし、自分で作ったオリジナルの歌詞を入力することもできる。1分足らずで、私たちはボーカル入りの楽曲に加えて歌詞、CDジャケットのような曲のイメージ画像までセットで手にすることができる。
こうして生成された音楽は、「Boomy」など一部の音楽生成AIではそのままSpotifyやApple Music等の音楽配信サービスにアップロードし、ストリーミング配信により再生数に応じた収益を得ることが可能になっている。
アーティストやレコード会社に広がる不安と対応
このような音楽生成AIによって生成された音楽をめぐっては、他のジャンルと同じく様々な論争が生じている。
現在公開されている音楽生成AIの中には、AIに学習させるデータとしてどのような楽曲を用いたのかということが明らかにされていないものも多い。
つまり、仮に学習データとしての利用が不適切である楽曲が利用されてしまっているとしても、現状ではユーザーに知る術がない。アーティストたち、もしくはレコード会社が自らの作品を学習材料として使用されていないか不安に感じるのは当然のことだろう。
2024年には、アメリカでソニーミュージック、ユニバーサルミュージックグループ、ワーナーレコードという音楽業界の大手レコード会社が、音楽生成AIモデルの訓練に音源が無断で使用されたとして、音楽生成AIの制作会社、SunoとUdioに対する訴訟を起こしている[1]。
一方で、ユニバーサルミュージックグループとローランド株式会社は戦略的パートナーシップを組み、音楽制作におけるAIの責任ある使用に関する声明として2024年3月に「AIによる音楽創造のための原則」を発表した[2]。
こうした状況の中、アメリカでは、AI開発者にAIモデルの訓練に使用した素材の開示を義務付け、著作者が自身の著作物が生成AIモデルの学習に利用されたかどうかを判断できるようにすることを目的とした法案(通称TRAIN法)が提出されている[3]。
AIによる変化をポジティブに歓迎する声も
もちろん、音楽生成AIに対し心配や懸念の声ばかりがあがっているわけではない。
音楽生成AIは、自らの創作活動に新たな刺激や一人では思い付かないようなアイディアを提案してくれるツールにもなり得る。実際、音楽生成AIの登場を歓迎し、今後の発展を楽しみにするコメントが一部のアーティストによってなされている[4]。
また、楽譜の書き方や楽器の演奏方法を知らずとも、テキストをプロンプトとして打ち込み音楽を生成できるようになったことで、より多くの人が「音楽を作る・演奏する」、つまり音楽をめぐる創作活動に参加できるようになるということも生成AIがもたらした変化だと言える。
音楽生成AIの開発・使用をめぐる諸影響の把捉や望ましい使用のあり方に関しては、検討すべきことが山積している。一方で、もはや生成AIのない世の中に戻ることは難しいだろうということも偽らざる事実である。
次回以降は、音楽生成AIの登場によって起こった変化やこれから起こり得る変化について、私たちが生成AIによって音楽を作ること/生成AIによる音楽を視聴することという2つの観点から、もう少し掘り下げて考えてみたい。
[1] これに対し、SunoとUdioはそれぞれ反論している。Udioは「既存の録音をデータとして利用し、さまざまな音楽スタイルについて分析し、人々が独自の新しい創作を行えるようにすることは「フェアユース」の典型だ」と述べた。Brittain, B. (2024, Auguast 2). Music AI startups Suno and Udio slam record label lawsuits in court filings. Reuters.
https://www.reuters.com/legal/litigation/music-ai-startups-suno-udio-slam-record-label-lawsuits-court-filings-2024-08-01/
[2] 「ユニバーサル ミュージック グループとローランドが人間の芸術性を高めるための 戦略的パートナーシップを構築 ~「AIによる音楽創造のための原則」を発表し音楽制作におけるAIの責任ある活用への協業を開始~」(2024.3.21). Universal Music Japan. https://www.universal-music.co.jp/press-releases/2024-03-21/
サポーターには、50以上の音楽関連企業、団体、大学などの研究機関が名を連ねている。
[3] Transparency and Responsibility for Artificial Intelligence Networks (TRAIN) Act。2024年11月に初めて提出され、2025年7月に再提出された。
[4] 「音楽生成AI『Suno AI』が話題 音楽家が好意的な反応を示すのは「特有の文化」が理由か」(2023.12.14)リアルサウンドテック. https://realsound.jp/tech/2023/12/post-1518951.html
David Guetta says the future of music is in AI (2023, Feburary 13). BBC NEWS. https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-64624525.amp
🖊️あなたの視点をお聞かせください(別ウィンドウで開く)
ご購入いただくと過去記事含むすべてのコンテンツがご覧になれます。
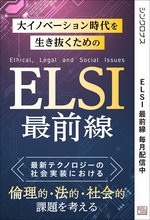
過去のコンテンツも全て閲覧可能な月額サブスクリプションサービスです。
🔰シンクロナスの楽しみ方
イノベーション時代のビジネスに欠かせないリテラシー「ELSI」を身につける、双方向プラットフォーム。専門家とのフラットな議論を通じて、未来を見据えた多角的な判断軸を手に入れよう。
- 記事連載:最新技術や制度の事例をもとに、ELSIの論点を専門家が解説
- フォーラム:読者の疑問や意見に専門家が応答し、議論を深める対話の場
- ニュースレター:注目ニュースや読者の声を、専門家のコメントとともに配信

生成AIの登場によって、音楽の作り方や演奏、そして聴いて楽しむ体験さえも大きく変わろうとしている。その一方で、著作権や文化への影響等、解決すべき課題も山積みだ。AI音楽は、私たちの音楽との関わり方をどのように変えていくのだろうか。音楽学・文化政策学等を専門とし、産学連携の研究にも取り組む肥後楽氏が、音楽生成AIをめぐる新たな問いを考える。(全3回)
※本コンテンツは、月額サブスクリプション『ELSI最前線』でも閲覧できます。
会員登録がまだの方は会員登録後に商品をご購入ください。