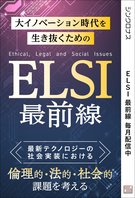わずか数行のテキストから楽曲が生成され、瞬く間に世界中に配信される——。
生成AIの登場によって、音楽の作り方や演奏、そして聴いて楽しむ体験さえも大きく変わろうとしている。その一方で、著作権や文化への影響等、解決すべき課題も山積みだ。AI音楽で事業を起こす事例も現れてきた今、AI音楽は、私たちの音楽との関わり方をどのように変えていくのだろうか。
最先端技術に関する倫理的・法的・社会的課題──「ELSI(エルシー)」の考え方をひも解き、社会とビジネスにおける実践的な視点を提供する連載「ELSI最前線」。今月は、音楽学・文化政策学等を専門とし、産学連携の研究にも取り組む肥後楽氏が、音楽生成AIをめぐる新たな問いを考える。(第2回/全3回)
💡この記事のポイント
- 現状の音楽生成AIでは複雑かつ長時間の楽曲生成は難しい。また、学習データの少なさや偏りから音楽の多様性に影響を及ぼす懸念がある。
- 意図した通りの楽曲を得るにはプロンプトを研ぎ澄ませ試行錯誤するプロセスが必要。AIの膨大なアウトプットからアイデアを選ぶのは人の役割である。
- 生成AIとの創作を通じて、自分が音楽をどのように選び、楽しんでいるのかを再発見することにもつながる。
🖊️技術と人のイノベーションをめぐる、専門家との議論に参加しましょう!


大阪大学社会技術共創研究センター特任助教。大阪大学大学院文学研究科単位取得退学。専門は、音楽学、文化政策学、協働形成。ELSIセンターでは「芸術とELSI」に関する探索的研究を推進すると共に、異分野を「つなぐ」人材として人社系産学連携の基盤構築をテーマとした研究に取り組む。最近の業績に「テクノロジーと音楽の結びつき―そして音楽生成AIへ」『フィルカル』9(2),(吉村汐七との共著、2024)、「ELSI/RRIをめぐる産学連携:大阪大学社会技術共創研究センターと株式会社メルカリmercariR4Dの事例から」『ELSI入門』第5章(丸善出版, 2025)など。プロフィール詳細
音楽生成AIの活用で楽曲制作はどう変わる?
「生成AIの登場によって、私たちは楽譜の書き方やコード進行をはじめとした作曲に関する専門的な知識を習得せずとも、自分の気分やその時のシチュエーションに応じた音楽を作ることができるようになるだろう。」
こんな言説を耳にすることがある。
第2回となる今回は、本当に私たちは音楽生成AIによって創作活動に気軽に参画することが可能になるのか?という点について考えてみたい。
音楽生成AIの技術的課題
生成AIによる音楽生成には、いくつかの技術的課題がまだ残されていることが指摘されている。
例えば現状の音楽生成AIでは、複雑な、それでいて一貫性を持った長時間の楽曲を生成することは難しい。
生成された音楽のクオリティという話以前に、単純に長さや用いられている楽器の種類の多さ(音色の多彩さ)という点だけをとってみても、40分程度の長さの交響曲のオーケストラ総譜をAIが一度に生成するにはまだ時間がかかりそうである。
また、音楽生成AIを開発する際の課題のひとつとして、AIモデルに学習させるデータセットが少ないことが挙げられている。
さらに、例えば学習データがクラシック音楽もしくは西洋のポップミュージックなど、特定のジャンルに偏って構成されていた場合、他のジャンルの音楽が出力されることはほぼなくなってしまう。こうした学習データの少なさや偏りが、音楽の多様性に深刻な影響を与える可能性がある。
しかしながらこうした技術的課題は、急速なスピードで改善されつつある。将来的には曲の長さやバリエーション、音質などに関して、今よりずっと滑らかに、より多様な音楽が生成可能になるはずで、現在は技術的発展の途上にあると捉えられるだろう。
例えばSuno AIは、複数回のヴァージョンアップにより出力できる曲の長さが初期の倍以上の長さ(最大8分間)となり、選択肢として示される音楽ジャンルも大幅に拡充された。
創作をする私たちの側にある課題
では、このような技術的課題が徐々に解消されていった場合、音楽生成AIによって私たちは自分の望む曲を自ら簡単に創作することができるようになるのだろうか。
何らかの音楽を生成することは可能だが、誰もが本当に意図した通りの作品に辿り着くことは難しいのではないか、というのが私の率直な感想である。...