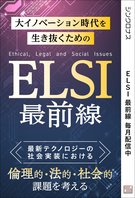急速に進化する科学技術は、私たちの生活や社会、ビジネスの在り方に大きな変化をもたらしている。その一方で、最先端技術に関する倫理的・法的・社会的な課題――「ELSI(エルシー)」が浮かび上がっている。技術が生み出す新たな可能性と向き合い、どのような未来を築いていくべきか。その答えを見つけるために、今こそ立ち止まり、考える必要がある。
本連載では、話題の新技術やビジネス動向を通じてELSIの考え方をひも解き、社会とビジネスにおける実践的な視点を提供する。今月は、AIやSNSなど先端技術を利用する私たちとELSIとの関係をめぐって、哲学、特に概念工学を専門とする鹿野祐介氏の論考をお届けする。(第1回/全3回)


大阪大学COデザインセンター特任講師。東北大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。同大学社会技術共創研究センター(ELSIセンター)を兼担。専門は哲学/概念工学。ELSIセンターでは、責任ある研究開発に関する実践研究とELSI人材の育成開発に取り組んでいる。共編著に『ELSI入門』(丸善出版, 2025)、訳書に『デジタルテクノロジーと時間哲学』(丸善出版, 2024)などがある。 >>プロフィール詳細
日常に先端技術が入り込む現代。私たちにできることは?
私たちは、日々気づかぬうちに、さまざまな先端技術の恩恵を受けている。利便性や快適さを享受する一方で、その裏側に潜むリスクにも少しずつ敏感になってきた。そして、近年では、こうしたリスクだけでなく、技術と社会との関係のもとで問われる「倫理的・法的・社会的課題(ELSI)」にも、関心が高まりつつある。
ここで、少し考えてみたい。ELSIに対して私たちには何ができるだろうか。いや、「私たちはELSIに対して何かしているだろうか」と問うべきかもしれない。
AIのサービスを使い、SNSで情報を発信し、便利さや快適さを享受する。その一つ一つの行動が実はELSIと無縁ではない。
たとえば、自動的にニュースを推薦してくれる機能に頼ることが日々取り入れている情報の偏りを助長する一因になっているかもしれないし、無意識に差別的な表現や画像に反応することがAIの学習過程に影響を与えているかもしれない。
また、SNSで気軽に投稿した写真や動画が、本人の同意なしに顔認識アルゴリズムの学習データとして利用される可能性があるという点も、プライバシーや情報利用の透明性をめぐる重要な問題である。
加えて、そうした大量の画像や映像がAIの性能を高め、結果として公共空間での監視や追跡の技術を支える土台となるとすれば、意図せずして監視社会の進展に間接的に加担してしまうことにもなりかねない(注1)。

認知度が増しているELSI、しかし……
近年、「ELSI」という言葉を耳にする機会が確実に増えてきている。かつては主にバイオテクノロジーの文脈で語られていたこの言葉が、いまやAIやビッグデータといった情報技術の急速な進展とともに、データビジネスやDXなどの社会的関心とも結びつくようになってきた。
2021年の調査によれば、「ELSI」という用語の認知度は、一般生活者で約20%、データビジネス従事者では約40%に達しており、その知名度は「エシカル消費」や「ESG投資」といった他の倫理・社会的関心事と肩を並べつつある(注2)。「ELSI」もまた時代を映すキーワードとなりつつある。
だが、そうした言葉の認知が進む一方で、「ELSI」とは具体的に何を指すのか、その内容についての理解はまだ十分に深まっていない。
古くはヒトゲノムの解析にもとづく遺伝情報の取り扱いと差別の問題から、現代ではAIが引き起こす差別的判断、ディープフェイクやハルシネーションといった虚偽情報の生成など、先端技術が日常のなかに入り込んでくるほどに、「ELSI」と呼ばれる問題の範囲はますます拡がりつつある。
しかし、これらの問題が「ELSI」であるとして、それらに対して誰がどのように対応するのだろうか。少なくとも現状は、技術者や研究開発に携わる一部の人に任せるものとして切り離されている。
科学技術と社会の間の空白
この記事のはじめでも触れたように、さまざまなELSIは、すでに社会のあちこちで顕在化しており、「何らかの対処が必要だ」とする世論も拡がりを見せている。ELSIが取り組むべき重要な課題だという認識は少しずつかもしれないが確実に浸透しつつある。
だが、その認識が実際の行動や制度設計、あるいは市民としての参加や議論の活性化といった形にまで結びついているかといえば、心もとないのが実情である。
「問題であることはわかっているが、どう関われるのかはわからない」——このような理念と実践のあいだに横たわる空白はなぜ埋まらないのだろうか。その要因として、ここでは、二つの「距離」——「言葉の距離」と「身体的な距離」に着目してみたい。
(注1)工藤 郁子「トラッキング技術:信頼・監視・個人をめぐる連環と緊張トラッキング技術」『ELSI入門』丸善出版、2025年
(注2)岸本 充生、長門 裕介、朱 喜哲「生活者・データビジネス従事者のELSI課題意識を読み解く」2022/08/22 (https://dentsu-ho.com/articles/8297))
🖊️あなたの視点をお聞かせください
記事に対する意見や質問を投稿できます。投稿いただいた内容はニュースレターや会員向け記事として紹介し、記事執筆者が応答します。ご購入いただくと過去記事含むすべてのコンテンツがご覧になれます。
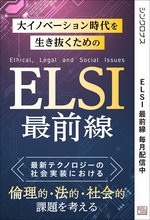
過去のコンテンツも全て閲覧可能な月額サブスクリプションサービスです。
🔰シンクロナスの楽しみ方
イノベーション時代のビジネスに欠かせないリテラシー「ELSI」を身につける、双方向プラットフォーム。専門家とのフラットな議論を通じて、未来を見据えた多角的な判断軸を手に入れよう。
- 記事連載:最新技術や制度の事例をもとに、ELSIの論点を専門家が解説
- フォーラム:読者の疑問や意見に専門家が応答し、議論を深める対話の場
- ニュースレター:注目ニュースや読者の声を、専門家のコメントとともに配信

AIサービスを使い、SNSで情報を発信する。私たちのこうした行動は、倫理的・法的・社会的にどのような影響を及ぼしているのか? AIやSNSなど先端技術を利用する私たちとELSIとの関係をめぐって、哲学、特に概念工学を専門とする鹿野祐介氏の論考をお届けする。(全3回)
※本コンテンツは、月額サブスクリプション『ELSI最前線』でも閲覧できます。
会員登録がまだの方は会員登録後に商品をご購入ください。