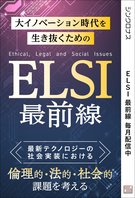急速に進化する科学技術は、私たちの生活や社会、ビジネスの在り方に大きな変化をもたらしている。その一方で、最先端技術に関する倫理的・法的・社会的な課題――「ELSI(エルシー)」が浮かび上がっている。技術が生み出す新たな可能性と向き合い、どのような未来を築いていくべきか。その答えを見つけるために、今こそ立ち止まり、考える必要がある。
本連載では、話題の新技術やビジネス動向を通じてELSIの考え方をひも解き、社会とビジネスにおける実践的な視点を提供する。今月は、AIやSNSなど先端技術を利用する私たちとELSIとの関係をめぐって、哲学、特に概念工学を専門とする鹿野祐介氏の論考をお届けする。(第3回/全3回)


大阪大学COデザインセンター特任講師。東北大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。同大学社会技術共創研究センター(ELSIセンター)を兼担。専門は哲学/概念工学。ELSIセンターでは、責任ある研究開発に関する実践研究とELSI人材の育成開発に取り組んでいる。共編著に『ELSI入門』(丸善出版, 2025)、訳書に『デジタルテクノロジーと時間哲学』(丸善出版, 2024)などがある。 >>プロフィール詳細
ELSIの「当事者」は誰なのか?
理念と実践とのギャップの背景には、もうひとつ見過ごされがちな要因がある。それは、当事者性の欠如である。
「当事者性」とは本来、ある問題や出来事に直接関与しているかどうかを基準に語られる。しかし、倫理的・法的・社会的課題(ELSI)のように複雑に構造化された問題を考えるときには、この理解だけでは不十分である。
たとえば、AIによる差別的な判断が生じた場合、それが自分に向けられたものでなければ「自分には関係がない」と考えてしまいがちである。しかし、果たしてそうだろうか。
AIが自分勝手に誰かを差別するということはありえない。その差別が生み出された背後には、AIが判断を下すために用意された膨大なデータ、アルゴリズムの設計、AIを生み出すことのできる社会制度、そして、日々の私たちの行動や選好がある。
AIは、私たちの社会が長年にわたり暗黙的に許容してきた価値観やバイアス、言語使用や文化、教育や制度などをただ機械的に再生産しているに過ぎない。つまり、AIが生み出す差別とは、私たちが暗黙裏に許容している差別なのである。
「差別的な判断」を出力するAIを生み出す構造のなかに、私たちは組み込まれている。私たちもまたそのようなAIを許容し、その前提を支えた人として「当事者」なのである。

「当事者性の欠如」とは
...