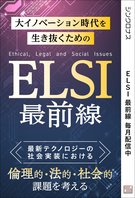生成AIに、話し相手になってもらうという人が増えている。愚痴をこぼせば、否定せずに耳を傾けてくれて、やさしい言葉も返してくれる──気づけば、そんなAIとの対話が感情のよりどころになっていた。もしもこのような、AIへの“依存”が進んだとして、それは果たして悪いことなのだろうか?
最先端技術に関する倫理的・法的・社会的課題──「ELSI(エルシー)」の考え方をひも解き、社会とビジネスにおける実践的な視点を提供する連載「ELSI最前線」。今月は、臨床哲学や哲学対話を専門とする鈴木径一郎氏が、生成AIの技術的発展と依存の問題について論じる。(第2回/全3回)
💡この記事のポイント
- 熊谷晋一郎は、依存症者は「依存しすぎているのではなく、いまだ十分に依存できていない人々だ」とする独自の視点を提示している。
- この考え方によれば、「依存」自体は悪いことではない。問題は、依存先の極端な少なさや、それによる特定のものへの依存度の深さにある。
- 生成AIを感情のケアに利用することは、一見依存先の増加に見えるが、本当に感情のケアに有益なのか、長期的に他の依存先を見つける能力を損なわないか、孤立を招かないかといった点を慎重に考慮する必要がある。
🖊️技術と人のイノベーションをめぐる、専門家との議論に参加しましょう!

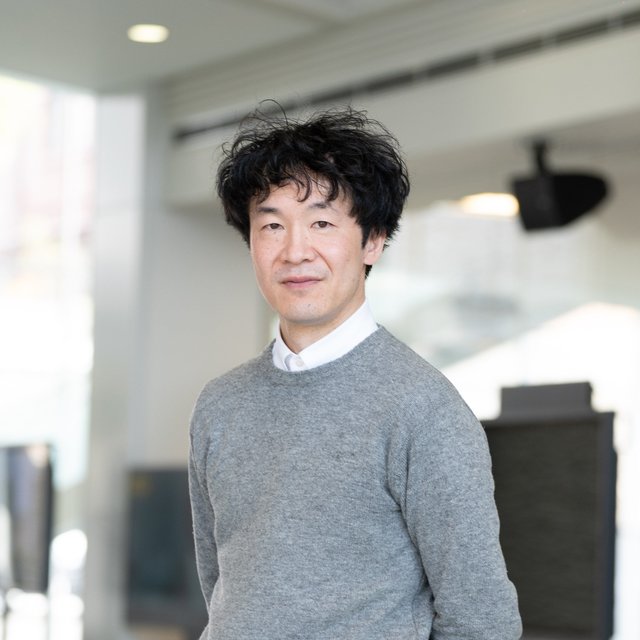
大阪大学社会技術共創研究センター(ELSIセンター)特任助教。大阪大学文学研究科博士後期課程単位取得退学。専門は臨床哲学・哲学プラクティス。ELSIセンターでは、さまざまなアクターとの哲学対話の実践経験を用いながら、多数の企業との「責任ある研究・イノベーション」に関する共同研究に従事している。共著に『哲学対話と教育』(大阪大学出版会, 2021)。プロフィール詳細
「依存」とはどういうことなのか
ということで、生成AIを感情のケアに用いていくことの影響や、より広くテクノロジーに関連した「アディクション」や「依存症」の問題を考える前提として、「依存」ということ自体についていくらか考えてみたい。
参考にするのは、生まれつき「脳性まひ」という障がいをもつ小児科医であり学者である熊谷晋一郎による、依存症と依存の関係についての議論である。
熊谷は『アディクションの地平線』(2022年)に収録された「依存症からの回復をめぐって」という示唆的な論考において、「何ものにも依存せずに生きている人など,存在しない」という「明らかな事実」を確認するところから始める——「あなたが毎日食べているお米は、誰が作っているのか。いつも身にまとっている衣服は誰が作っているのか〔…〕人間は誰しも、生活のほとんどを自力では行っていない〔…〕私たちの日常は、自己身体、モノ、他者身体、重力、大気、制度、慣習といった膨大な物理的・社会的環境の支えに「依存」しているのである」。
この「明らかな事実」については、「依存」という言葉をまずはニュートラルに広くとらえてみるならば、その通りであるといえるだろう。
そして、このように広く「依存」をとらえたうえで熊谷は、依存症者は「依存しすぎているのではなく、いまだ十分に依存できていない人々なのではないか」という興味深い仮説を提案するのである。
障がいと依存の関係に関する議論
...