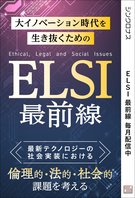急速に進化する科学技術は、私たちの生活や社会、ビジネスの在り方に大きな変化をもたらしている。その一方で、最先端技術に関する倫理的・法的・社会的な課題――「ELSI(エルシー)」が浮かび上がっている。技術が生み出す新たな可能性と向き合い、どのような未来を築いていくべきか。その答えを見つけるために、今こそ立ち止まり、考える必要がある。
本連載では、話題の新技術やビジネス動向を通じてELSIの考え方をひも解き、社会とビジネスにおける実践的な視点を提供する。今月は、AIやSNSなど先端技術を利用する私たちとELSIとの関係をめぐって、哲学、特に概念工学を専門とする鹿野祐介氏の論考をお届けする。(第2回/全3回)


大阪大学COデザインセンター特任講師。東北大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。同大学社会技術共創研究センター(ELSIセンター)を兼担。専門は哲学/概念工学。ELSIセンターでは、責任ある研究開発に関する実践研究とELSI人材の育成開発に取り組んでいる。共編著に『ELSI入門』(丸善出版, 2025)、訳書に『デジタルテクノロジーと時間哲学』(丸善出版, 2024)などがある。 >>プロフィール詳細
「倫理的」「法的」「社会的」と先端技術の距離
理念と実践のあいだに横たわる空白が埋まらない要因のひとつとして、言葉がもつ「距離」があるのかもしれない。
「倫理的」・「法的」・「社会的」といった言葉は、どこかで聞いたことのある言葉として、漠然とであれ、何らかのイメージを連想させてくれる。たとえば、「倫理的」と聞いて、人に迷惑をかけないことや、正しい行いを思い浮かべる人もいるだろう。「法的」であれば、法律やルールを守ること、「社会的」ならば、地域との関係や世論、常識といったものが連想されるかもしれない。
しかし、こうした言葉を、AIやビッグデータ、バイオテクノロジーといった先端技術と結び付けようとするとき、思い浮かべるイメージは途端に曖昧になる。
「倫理的なAI」とは何なのか。「バイオテクノロジーをめぐる法的課題」とはどのようなものなのか。「社会的に望ましいビッグデータの活用」とは具体的にどのような状態なのか。
「倫理」や「法」、「社会」といった言葉と、科学技術の関係性を具体的に思い描くことはそれほど簡単なことではない。

「言葉はわかるが、意味がわからない」
このような問題は「意味の連関」に関わる。意味の連関とは、...