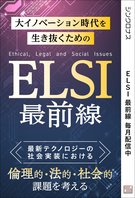生成AIに、話し相手になってもらうという人が増えている。愚痴をこぼせば、否定せずに耳を傾けてくれて、やさしい言葉も返してくれる──気づけば、そんなAIとの対話が感情のよりどころになっていた。もしもこのような、AIへの“依存”が進んだとして、それは果たして悪いことなのだろうか?
最先端技術に関する倫理的・法的・社会的課題──「ELSI(エルシー)」の考え方をひも解き、社会とビジネスにおける実践的な視点を提供する連載「ELSI最前線」。今月は、臨床哲学や哲学対話を専門とする鈴木径一郎氏が、生成AIの技術的発展と依存の問題について論じる。(第3回/全3回)
💡この記事のポイント
- 依存について考える際には、「苦痛」が重要な概念である。小さな「予測誤差」(=予期を裏切る体験)に伴う苦痛とうまく付き合うことが、依存からの回復において重要だという指摘がある。
- 現代の情報環境は、小さな予測誤差を回避する「なめらかな流れ」を提供しがちだ。しかし、この「つまずき」や「ひっかかり」といった苦痛に耐える力が奪われる恐れがある。
- 生活の「なめらかさ」を追求しすぎず、適度な苦痛を積極的に受け入れ、活用していくことが、テクノロジーと向き合う上で重要だ。
🖊️技術と人のイノベーションをめぐる、専門家との議論に参加しましょう!

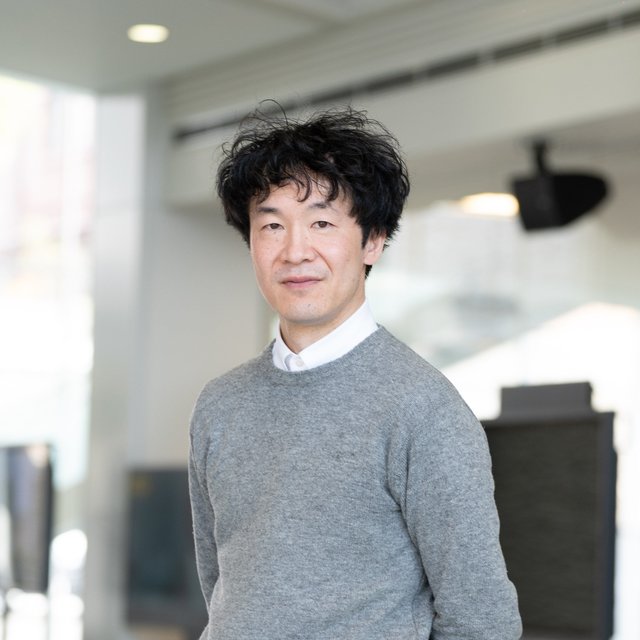
大阪大学社会技術共創研究センター(ELSIセンター)特任助教。大阪大学文学研究科博士後期課程単位取得退学。専門は臨床哲学・哲学プラクティス。ELSIセンターでは、さまざまなアクターとの哲学対話の実践経験を用いながら、多数の企業との「責任ある研究・イノベーション」に関する共同研究に従事している。共著に『哲学対話と教育』(大阪大学出版会, 2021)。プロフィール詳細
テクノロジーに囲まれて生きる時代に「苦痛」をどう考えるか?
ここで最後に、生成AIの感情調整への利用も含め、広く「情報環境と関連したアディクション」の問題に参照できる議論として触れておきたいのが、「苦痛の再評価」あるいは「苦痛の活用」についての議論である。
苦痛の適切な活用は「デジタル方式でドーパミンを運んでくる現代」をいかに生きるかという文脈において、スタンフォード大学の依存症医学部門メディカルデイレクターであるアンナ・レンブケが提案した方法の一つでもある。
レンブケがその前提として指摘しているのは、依存症に大きく関わっている脳の報酬系は「快」だけでなく「苦痛」も扱っており、しかも、両者はシーソーのようにバランスしているということである。現代の依存症的状況の拡大の背景には快苦のアンバランスがあり、快へのアクセスの増加だけでなく、苦痛の回避の一般化が関わっている。
快の体験はすぐにそれをバランスさせる不快をもたらすし、快の機会の増加は快への感受性を下げながら不快への感受性を高めるのだが、快楽の追求ではない単なる不快の回避も、不快への感受性を高めてしまう。
象徴的な事例は向精神薬の恒常的な利用によるうつ病のケースであるが、これは、苦痛の回避の恒常化による恒常的な苦痛という、私たちの時代にありふれたパターンの一例である。
痛みを回避する手段の増加と説明不能な疼痛の増加の関係や、気晴らしの氾濫による退屈の増加、これらをある程度まとめて説明できるのが脳の報酬系のメカニズムであり、そこで着目されるのが、苦痛の活用というわけである。
「回復」のための苦痛の活用
...