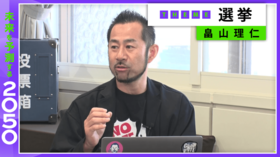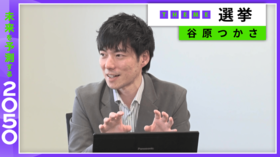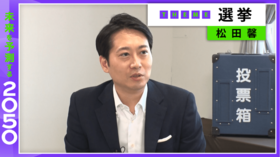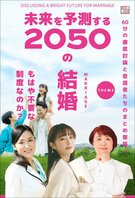2050年の未来を予測する討論型コンテンツ。第1回は「選挙」をテーマに4人の登壇者に議論をしていただきました。
本コンテンツでは、討論後に各登壇者の方から、議論を踏まえたうえで、新たに得た気づきや、語りつくせなかったことについてご寄稿いただきます。
今回は主権者教育の重要性についてジャーナリストのたかまつななさんに語っていただきました。
与野党で折り合いをつけられなければ「民主主義の危機」を招く
今回の対談で強く感じたのは、「一堂に集まって真剣に議論することの大切さ」です。近年はそうした場が少なく、意見の違いを持ちながらも建設的な話し合いができたことは貴重でした。
参院選では与党が過半数を割り、国民は現政権に「NO」を突きつけました。しかし、自民党内では石破氏への評価が定まらず、混乱していました。旧安倍派による「石破おろし」が表面化しても、裏金問題の当事者であるため国民の反発を招き、むしろ党内対立を深めています。
その結果、国民には「国民生活よりも派閥内の勢力争いが優先されている」という印象を与えています。
本来であれば、減税など与野党が一致を見出せるテーマもあるはずです。私自身は安易な減税には賛成ではありませんが、政策協議や現実的な合意形成を進めることが急務でしょう。民主主義は意見の違いを前提に、自由や権利を尊重しながら「落としどころ」を探る営みです。ところが今の政治には折り合いをつける姿勢が見えません。
ドイツでは高校の授業でも「折り合いをつける力」を学びますが、日本の政治はブラックボックス化しており、その過程が表に出ず、ポジショントークばかりが目立っています。
参政党に投票した人すべてが排外的だとは思いませんが、「日本人ファースト」の姿勢は文化共生の議論を難しくしています。社会問題やデータに基づく解決策よりも立場の主張が先行し、「対話すること自体が罪」...