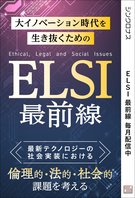わずか数行のテキストから楽曲が生成され、瞬く間に世界中に配信される——。
生成AIの登場によって、音楽の作り方や演奏、そして聴いて楽しむ体験さえも大きく変わろうとしている。その一方で、著作権や文化への影響等、解決すべき課題も山積みだ。AI音楽で事業を起こす事例も現れてきた今、AI音楽は、私たちの音楽との関わり方をどのように変えていくのだろうか。
最先端技術に関する倫理的・法的・社会的課題──「ELSI(エルシー)」の考え方をひも解き、社会とビジネスにおける実践的な視点を提供する連載「ELSI最前線」。今月は、音楽学・文化政策学等を専門とし、産学連携の研究にも取り組む肥後楽氏が、音楽生成AIをめぐる新たな問いを考える。(第3回/全3回)
💡この記事のポイント
- 「作業用BGM」のように作者を意識しない場面だけでなく、ライブパフォーマンスのように「誰の作品か」が重視される場面でさえ、AIが創作や演奏の一部を担う可能性がある。
- 生成AI音楽が氾濫することで、視聴者は聴きたい曲を見つけにくくなり、アーティストは楽曲の認知度を高めにくくなるリスクがある。
- 飛躍的なスピードで大量に作成可能な生成AIによる音楽を、市場の中でどのように位置づけ共生していくべきか、考え続けなければならない。
🖊️技術と人のイノベーションをめぐる、専門家との議論に参加しましょう!


大阪大学社会技術共創研究センター特任助教。大阪大学大学院文学研究科単位取得退学。専門は、音楽学、文化政策学、協働形成。ELSIセンターでは「芸術とELSI」に関する探索的研究を推進すると共に、異分野を「つなぐ」人材として人社系産学連携の基盤構築をテーマとした研究に取り組む。最近の業績に「テクノロジーと音楽の結びつき―そして音楽生成AIへ」『フィルカル』9(2),(吉村汐七との共著、2024)、「ELSI/RRIをめぐる産学連携:大阪大学社会技術共創研究センターと株式会社メルカリmercariR4Dの事例から」『ELSI入門』第5章(丸善出版, 2025)など。プロフィール詳細
AI「が」いいのか、AI「でも」いいのか
第2回では、生成AIによって私たちが音楽を作る時について検討してきた。今回は、私たちが生成AIによる音楽を聴く時について想像してみたい。
生成AIによる音楽「が」聴きたいと思う時とは、どんな時だろうか。
もしくは、どんな時に生成AIによる音楽「でも」良いと思うだろうか。
この問いについて考えようとする時、私たちは必然的に「我々は普段その音楽が「誰のものか」についてどれくらい意識しているのか?」という問いについて考えなければならない。
私たちは、作者についてどのくらい意識しながら音楽を聴いているだろうか? 作者を意識せずに音楽を聴いているのは、どのような時だろうか?
今聴いている音楽は「誰の作品か?」
作者が誰かを考えないで音楽を聴いているシチュエーションとして真っ先に思い浮かぶのはBGMだ。
YouTubeには、【作業用BGM】というタイトルでさまざまなシチュエーションに合わせたBGMの動画がアップされている。このような音楽の系譜のひとつとして、生成AIによる音楽が活用される可能性は十分にあるだろう。
逆に、どんな作者がどんな思いを込めて作った作品かということが大きな意味を持つシチュエーションとしては、...