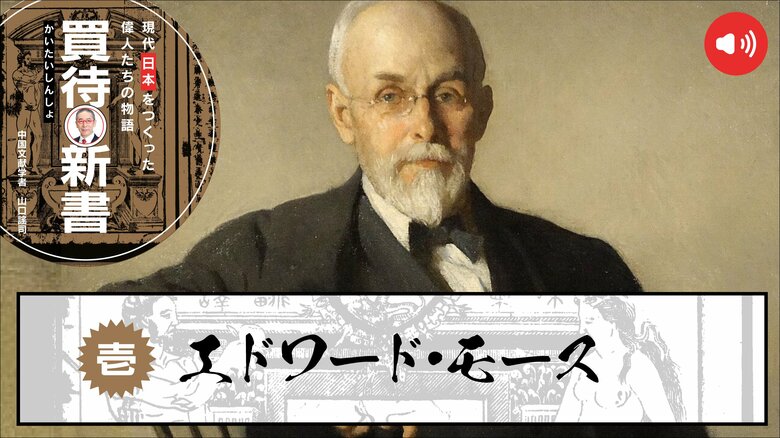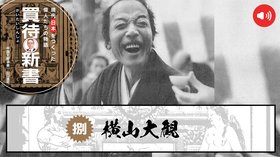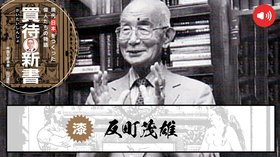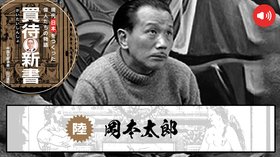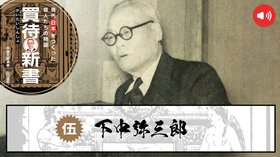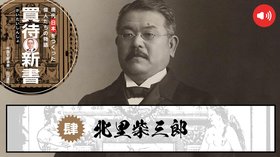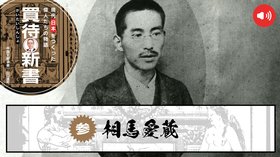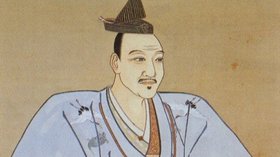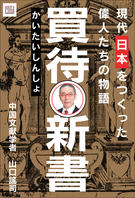「天下人」と呼ばれる武将や後世に名を残した文化人など、知名度の高い人物のほかにも、私たちの人生や身近な生活に影響をもたらした偉人がたくさんいます。
そんな名前だけは知っていてもどんな人物なのか? そもそもこの人は誰? など、幕末から平成にかけて活躍した偉人の生涯、功績、知られざるエピソードを、テレビやラジオで活躍する作家・山口謠司さんが音声でわかりやすく、楽しく紹介します。
ちょっと知りたい、でも時間がない……という方にぴったりのコンテンツです。
「買待」という言葉は孔子の言葉です。「買いを待つ人」という読み方をします。
「自分は社会のために役に立つ人として活躍する準備ができています。さあ、私を使ってください」という意味です。
後世、偉人と呼ばれるようになった人にもいろんな苦労があり、複雑な思いがありました。
皆1人1人が社会が有益に自分を使ってくれることを待つ、「買いを待つ人」だったんです。
彼らの人生をたどることで、我々の自分の足元を見直し、彼らの精神を学ぶことができればなと思います。(山口謠司)
*第1回は無料でお楽しみいただけます
*第2〜8回は各回単品(220円)でもお楽しみいただけます
第2回 渋沢敬三(7/2公開)
第3回 相馬愛蔵(7/9公開)
第4回 北里柴三郎(7/16公開)
第5回 下中弥三郎(7/23公開)
第6回 岡本太郎(7/30公開)
第7回 反町茂雄(8/6公開)
第8回 横山大観(8/13公開)
*第2回「渋沢敬三の生涯、渋沢栄一の孫、戦後のインフレ対策に取り組んだ「最後のエリート」」はこちらよりお楽しみいただけます
*第1回の内容は記事でもお楽しみいただけます。
皆さんこんにちは。作家の山口謠司です。今回より買待新書(かいたいしんしょ)というお話をしたいと思います。
「買待」という言葉は孔子の言葉です。「買いを待つ人」という読み方をします。
「自分は社会のために役に立つ人として活躍する準備ができています。さあ、私を使ってください」という意味です。
後世、偉人と呼ばれるようになった人にもいろんな苦労があり、複雑な思いがありました。
皆1人1人が社会が有益に自分を使ってくれることを待つ、「買いを待つ人」だったんです。
彼らの人生をたどることで、我々の自分の足元を見直し、彼らの精神を学ぶことができればなと思います。
明治から平成にかけて活躍した、知られているようで実は知られていない8人の方を紹介したいと思います。
文献学者、山口謠司として選んだ8人というのは、ずっと死ぬまで子供の心を捨てなかった人です。
一生懸命に生きた人たち。そういう人たちを8人選んでお話をさせていただきます。
第1回目は、シルベスター・モース、大森貝塚を発見したことで知られるアメリカ人、モースという人のお話です。
縄文という名前を作った人
大森貝塚、皆さん行ったことありますか。史跡になっています。縄文時代の縄文という名前を作った人、それがモースです。
縄文という言葉は後から日本語になったものなんですけれども、モースはアメリカ人なので、論文の中で、「cordmark」「pottery」、縄目模様の土器が使われていた時代のことを縄文時代と呼びました。
縄文の文様のある土器を使っていた時代、つまり縄文時代の日本人が日本という国に暮らしていたんだということを世界に初めて知らしめたのはこのモースだったんです。
モースが、今品川にありますが、大森貝塚の調査をしたのは1877年、年号で言いますと明治10年のことです。
モースは、アメリカから船に乗って横浜までやってきます。
横浜について、東京の領事館に行かないといけないよということを言われて、汽車に乗ります。
今のように早い電車じゃありません。ゆっくりゆっくり、ガッタンゴットン、ガッタンゴットン。
横浜から東京新橋まで来る汽車の中で珍しくて、右、左きっと見ていたんだと思います。
そしたら、大森を通過した時に、うわ。貝塚……貝塚を発見したんですね。
日本人にとってはなんでもない場所でした。でも、モースにとってはこれプレゼントだったんです。
実はモースが横浜に着いたのは6月18日。彼の誕生日の日でした。誕生日の日に、自分が1番日本に来て調べたかった貝塚を見ることができたんです。もう39歳の時でした。
東大の教授に
誕生日のプレゼント、もう一つありました。新橋の駅に着くと、外山正一(とやままさかず)という人が待っていたんです。
外山正一という人は東京大学の総長をしていた人ですけれども、明治10年というのは東京大学を9月から開こうねという時だったんですね。
モースが来たのは6月18日だったので、東大が開学する3ヶ月前のこと。
外山正一はいい学者で、東大の先生になってくれる人がいないかしらと言って探していたところだったんですけども、運良くモースがやってきたというんで、モースを新橋で待っていたんです。
モースは外山のことなど知りませんでした。でも、外山はモースに言うんです。
「先生のミシガン大学での進化論の公開講義を、僕は感銘を受けて聞いたことがあったんです」
こういう先生が東大の先生になってくれたらなと思っていたのに、そこに先生が来てくれるなんて、なんと嬉しいことでしょうと言って、日本に初めてできた大学の進化論の先生として、モースは招聘を受けたんですね。
その時のお給料は今の値段にして約5000万円とも6000万円とも言われています。そのうえ家も用意してあるから、何も心配することないよと言うんです。すごい誕生日のプレゼントですね。
モースはまさに「買いを待つ人」。世の中に自分は活躍できる準備ができていることを知らしめたいと思って日本に来たのかもしれませんが、そういう思いはもしかしたらなかったのかもしれません。
自分は5000万円、6000万円の給料をもらう人間としてできているかどうか、自分で確かめることもまだできていませんでした。
日本に来た理由
モースが研究していたのは、古代の貝の研究です。
貝といっても、本当は貝ではない、今では腕足動物と言われているものですけれども、アメリカには数種類しかいないという風に言われていました。
でも、日本に行くと、腕足動物、古代の貝のようなものが生きたままいっぱいいるんだよという噂を聞いていたんですね。
それで、モースは日本に行ってみたいと言って、いろんなところで公開講義をしながら、いろんな人たちから少しずつのお金をもらって、授業をしてお金を貯めて、やっとの思いで日本に来たんです。
モースは進化論を書いたダーウィンの友達です。
進化論が出版された年にモースは進化論を買って、そしてダーウィンに直接、僕も先生と同じ意見ですということを手紙でやり取りしていたんです。
そういう人で、キリスト教を全く信じていませんでした。
なぜかと言いますと、自分の弟が小さい時に亡くなってしまいます。
小さな弟は洗礼を受けていませんでした。そしたら、教会の神父さんが、洗礼を受けてない子供は教会の中に遺体を埋葬することはできないんだと言って、自分の弟は遠いところに埋葬されてしまったんですね。
そんなことがあるものか、我々は本当に神の子供なのかということをモースはその時に思ったそうです。
それから、キリスト教系の小学校に行くんですけれども、机を彫刻刀で彫って遊びをしたんだそうです。それで、小学校を辞めさせられてしまいます。
辞めさせられたおかげだったのか知りませんけれども、モースは子供の頃からカタツムリや貝をいっぱい集めて自分で標本を作っていたんです。
でも、大人になって生活をしないといけません。
ハーバード大学にある比較動物学博物館、そこにルイ・アガシーという先生がいらっしゃいました。
その人が雇ってくれたんですけれども、この人、モースが作った標本を全部自分のものにしてしまったんですね。
そんなこともあって、モースは、もっともっと人が知らない貝を探したいんだと言って日本にやってきます。
そして、先程言ったように、大森貝塚を発見し、調査報告書がネイチャーに掲載されることになるんです。
友達の1人にビゲローというアメリカ人がいました。このビゲローとモースは2人で話をします。
「日本はこれから近代化していくでしょ。おそらく1900年、1世紀を迎えたら、この我々が知っている今の日本ではなくなってしまうよ。近代化がどんどん進んで、今までずっと守り続けてこられた古い日本はなくなってしまうに違いない」
そう言われてから、モースは民具や陶器をとにかく集め始めます。その数、約1万点以上。今、ボストン美術館に所蔵されています。
そして、自分がもう研究が終わるよと言った時には、自分が持っていた蔵書を全て東大に寄贈するんです。今、東京大学付属図書館にモース文庫というのがあります。
モースという人が、自分がたくさんのお給料を頂いて研究をたくさんさせていただいた、そのお礼に本を全部寄贈したその東大の書物、我々見ることができますので、ぜひ東大に行って見てみてください。
今日は、シルベスターモース、大森貝塚を発見したことで知られるアメリカ人、モースのお話をさせていただきました。
次回は、日本銀行総裁になった渋沢栄一の孫、渋沢敬三さんのお話をしたいと思います。
渋沢敬三さんの言葉大事なことは主流にならぬこと。これをモットーに自分の夢を実現した最後のエリートと呼ばれています。
「買いを待つ人」お相手は作家の山口謠司でした。
音声制作/EAU
ご購入いただくと過去記事含むすべてのコンテンツがご覧になれます。
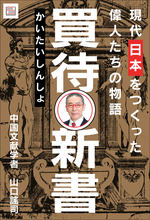
テレビやラジオで活躍する作家・山口謠司さんが、幕末から平成にかけて活躍した偉人の生涯、功績、知られざるエピソードを音声でわかりやすく紹介します(全8回)。*第1回は無料、第2〜第8回は単品での販売もあります(220円)
第1回(無料)エドワード・モース
大森貝塚を発見、日本の考古学の発展に尽力
第2回 渋沢敬三(7/2公開)
第3回 相馬愛蔵(7/9公開)
第4回 北里柴三郎(7/16公開)
第5回 下中弥三郎(7/23公開)
第6回 岡本太郎(7/30公開)
第7回 反町茂雄(8/6公開)
第8回 横山大観(8/13公開)
会員登録がまだの方は会員登録後に商品をご購入ください。