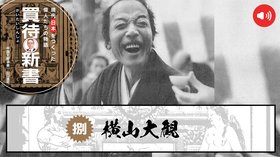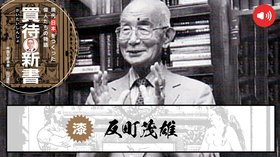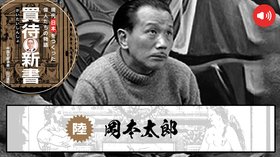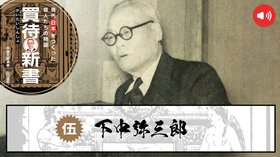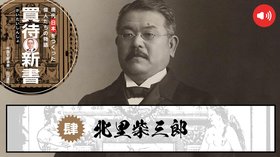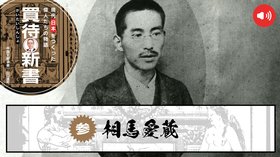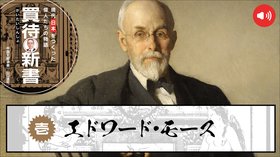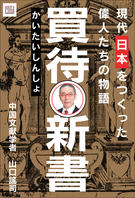「天下人」と呼ばれる武将や後世に名を残した文化人など、知名度の高い人物のほかにも、私たちの人生や身近な生活に影響をもたらした偉人がたくさんいます。
そんな名前だけは知っていてもどんな人物なのか? そもそもこの人は誰? など、幕末から平成にかけて活躍した偉人の生涯、功績、知られざるエピソードを、テレビやラジオで活躍する作家・山口謠司さんが音声でわかりやすく、楽しく紹介します。
ちょっと知りたい、でも時間がない……という方にぴったりのコンテンツです。
最終回は、「趁無窮(無窮を追う)」人ということで、横山大観を紹介したいと思います。
「買待」という言葉は孔子の言葉です。「買いを待つ人」という読み方をします。
「自分は社会のために役に立つ人として活躍する準備ができています。さあ、私を使ってください」という意味です。
後世、偉人と呼ばれるようになった人にもいろんな苦労があり、複雑な思いがありました。
皆1人1人が社会が有益に自分を使ってくれることを待つ、「買いを待つ人」だったんです。
彼らの人生をたどることで、我々の自分の足元を見直し、彼らの精神を学ぶことができればなと思います。(山口謠司)
*第1回「エドワード・モースー大森貝塚を発見、日本の考古学の発展に尽力した偉人の生涯」は無料でお楽しみいただけます
*第2〜8回は各回単品(220円)でもお楽しみいただけます
第2回 渋沢敬三(7/2公開)
第3回 相馬愛蔵(7/9公開)
第4回 北里柴三郎(7/16公開)
第5回 下中弥三郎(7/23公開)
第6回 岡本太郎(7/30公開)
第7回 反町茂雄(8/6公開)
第8回 横山大観(8/13公開)★この記事です!
大きく観る=大観
横山大観という人は富士山の絵をいっぱい描いた人です。片岡球子さんという人も富士山いっぱい描いていますね。
皆さんやっぱり富士山大好きですよね。一生のうち日本人で富士山を描いたことがないという人はいないんじゃないかと思いますが、日本画の世界で、富士山のような存在となった横山大観という人。この人も富士山が大好きでした。日本を象徴するものだったからでしょう。
厳島神社に所蔵される横山大観の作品に『屈原』と題するものがあります。
そして、東京国立博物館には『瀟湘八景』という重要文化財に指定されているものがあります。
これら2つの絵は、紀元前300年頃の中国の戦国時代に、楚という国が秦に滅ぼされることを憂いて自殺した憂国の死、屈原という人の思いを描いたものです。
富士山同様、これもまた中国の故事を使って、横山大観が自らの愛国心を表した絵だったんです。
屈原が書かれたのは明治31年、1898年のことです。横山大観は31歳になっていました。
大観の年齢は美術史に詳しい人でなくても簡単です。明治元年に生まれたということになっています。1868年ですね。夏目漱石も同じ年に生まれています。
15、6歳の頃から絵に興味を抱き、デッサンを習っていきますけれども、明治22年、今の東京藝術大学ですね、東京美術学校が開校するという時に、「デッサンの受験者は大量にいる、もしかしたら落ちてしまうかもしれない」というんで、急遽、日本画・毛筆に転身して、東京美術学校の日本画家に入学します。第1期生ですね。
ここで5歳年上の自分の恩師になる人と出会います。
岡倉天心、そして画家、菱田春草という人です。
卒業後、京都市立美術工芸学校、今の京都市立芸術大学です。ここで古い家を数多く模写して、大観、大きく観るという画号を使い始めます。これもまた中国の古典『荘子』という本に由来するものです。
大きく観る、十分に物事の道理を見抜いて心に獲得するという意味の言葉、大いに天下を見てやろうという言葉に由来しています。
横山大観が日本画の巨匠として、世界に日本画というものはこんなに素晴らしいものなんですよということを広めていったのは、東京美術学校の校長だった岡倉天心の力によるところが大きいと思います。
*続きはコンテンツ購入後にお楽しみいただけます
...