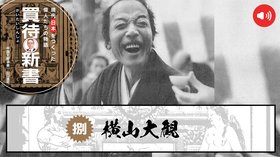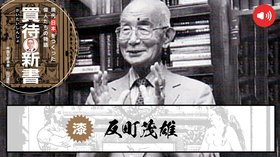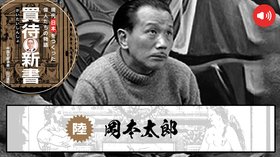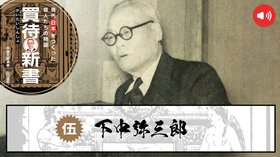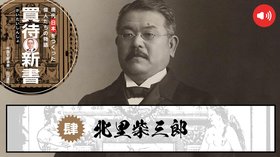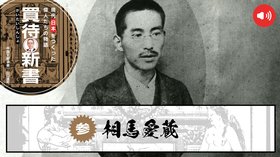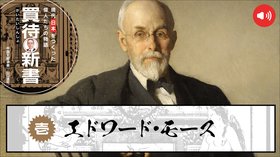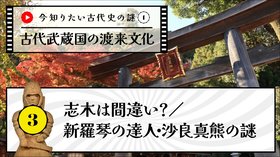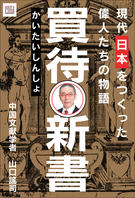「天下人」と呼ばれる武将や後世に名を残した文化人など、知名度の高い人物のほかにも、私たちの人生や身近な生活に影響をもたらした偉人がたくさんいます。
そんな名前だけは知っていてもどんな人物なのか? そもそもこの人は誰? など、幕末から平成にかけて活躍した偉人の生涯、功績、知られざるエピソードを、テレビやラジオで活躍する作家・山口謠司さんが音声でわかりやすく、楽しく紹介します。
ちょっと知りたい、でも時間がない……という方にぴったりのコンテンツです。
「買待」という言葉は孔子の言葉です。「買いを待つ人」という読み方をします。
「自分は社会のために役に立つ人として活躍する準備ができています。さあ、私を使ってください」という意味です。
後世、偉人と呼ばれるようになった人にもいろんな苦労があり、複雑な思いがありました。
皆1人1人が社会が有益に自分を使ってくれることを待つ、「買いを待つ人」だったんです。
彼らの人生をたどることで、我々の自分の足元を見直し、彼らの精神を学ぶことができればなと思います。(山口謠司)
*第1回「エドワード・モースー大森貝塚を発見、日本の考古学の発展に尽力した偉人の生涯」は無料でお楽しみいただけます
*第2〜8回は各回単品(220円)でもお楽しみいただけます
第2回 渋沢敬三(7/2公開)
第3回 相馬愛蔵(7/9公開)
第4回 北里柴三郎(7/16公開)
第5回 下中弥三郎(7/23公開)
第6回 岡本太郎(7/30公開)★この記事です!
第7回 反町茂雄(8/6公開)
第8回 横山大観(8/13公開)
皆さんこんにちは。作家の山口謠司です。今回より買待新書(かいたいしんしょ)というお話をしたいと思います。
「買待」という言葉は孔子の言葉です。「買いを待つ人」という読み方をします。
「自分は社会のために役に立つ人として活躍する準備ができています。さあ、私を使ってください」という意味です。
後世、偉人と呼ばれるようになった人にもいろんな苦労があり、複雑な思いがありました。
皆1人1人が社会が有益に自分を使ってくれることを待つ、「買いを待つ人」だったんです。
彼らの人生をたどることで、我々の自分の足元を見直し、彼らの精神を学ぶことができればなと思います。
明治から平成にかけて活躍した、知られているようで実は知られていない8人の方を紹介したいと思います。
文献学者、山口謠司として選んだ8人というのは、ずっと死ぬまで子供の心を捨てなかった人です。
一生懸命に生きた人たち。そういう人たちを8人選んでお話をさせていただきます。
今回は、母と父への愛で新しい芸術の地形を開いた爆発の人、岡本太郎の話をしたいと思います。
それまでの日本の芸術とは全く異質
大阪府吹田市千里にちょっと変わった塔のモニュメントがそびえたっていますね。
「太陽の塔」、高さ70m、およそ20階建てのビルに相当します。
その白い巨体には、背面に黒色で書かれた顔のある太陽、正面のお腹の部分にも大きな目をした彫刻の顔。そして等の一番上には金色に輝く顔、白い、そして角のような手が2本左右に出て、両脇に赤い縦のラインがギザギザと入っています。爆発してますね……!
太陽の塔と名付けられたこの塔は、1970年に日本万国博覧会「Expo'70」(大阪万博)のために作られました。作ったのは岡本太郎という芸術家です。
テレビやラジオの電波を発するための塔ではありません。中は空洞になってます。生命の木と呼ばれるものが4、5mの高さで伸びています。
単細胞生物から人類の誕生までの長い歴史を、三葉虫、ボルボックス、アンモナイト、プテラノドン、ゴリラ、オラウータン、チンパンジー、ネアンデルタール人、ジクロマニオン人とかいうものの模型が飾られて、電気仕掛けで動くようになっていました。
さすが「Expo'70」。行かれたことありますか。
人は螺旋階段を登りながら、単細胞生物から人類までの歴史をたどることができるようになっているんです。
当時の日本は、こんなことができる芸術家という人はほかに誰もいませんでした。
できた時にみんな、この太陽の塔を「牛乳瓶のお化け」とか「日本の恥辱」と言って批判したんです。でも、それまでの日本の芸術とは全く異質の「タロウ・オカモト」という国際的な芸術家の作品が、ここで多くの人に見られることになったんですね。
1970年3月14日から9月13日まで183日間開催された大阪万博の来場者数は、およそ6422万人とされています。
この年、我が国は、太平洋戦争が終わってからちょうど25年目になっていました。
高度成長と呼ばれる最後の段階に差し掛かってはいましたが、1964年に行われた東京オリンピックに引き続き、大阪で万博が開かれるということで、日本には特需の風が吹き荒れていたんです。
その当時の首相は佐藤栄作、アメリカ大統領はニクソン。日米安全保障条約の改正に反対する動きもありましたが、それにしても経済的な発展というのは人々の心に大きな夢と希望を沸かせます。
ちなみに、1970年代、日本列島改造論で有名な田中角栄が首相になって、全国に及ぶ高速道路や新幹線など、インフラがどんどん整備されていくことになってきますね。
土木関連事業で経済は潤いと豊かさをもたらしている時代でした。みんなが大阪万博を訪れ、太陽の塔を見たいという気持ちになったんです。
岡本太郎という人は小柄な人でした。身長156cm、でも体中から力をみなぎらせていらっしゃいました。僕は学生の時に岡本太郎さんの青山のお宅を何回も訪ねて、とっても親しくお話をさせていただいたことがあります。
*続きは音声でお楽しみください
音声制作/EAU
...