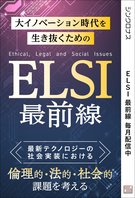「自衛隊が、電磁波で錆を防ぐと謳う謎の装置を導入しかけていた」「香川県が配布した教育教材に、根拠の乏しい“脳科学”が使われていた」——。
こうした怪しげな「疑似科学」が、行政や教育現場を通じて私たちの社会に静かに入り込み、税金や公共の信頼を蝕んでいる。SNSで注目を集めたこれらの事例も、氷山の一角にすぎない。今この瞬間も私たちの生活のすぐそばで、おかしな技術や理論が、まるで当然のように採用されつつあるかもしれない。
最先端技術に関する倫理的・法的・社会的課題──「ELSI(エルシー)」の考え方をひも解き、社会とビジネスにおける実践的な視点を提供する連載「ELSI最前線」。今月は、倫理学を専門とする長門裕介氏が、私たちの日常の中に巧妙に入り込む「地味な疑似科学」を考える。(第2回/全3回)
💡この記事のポイント
- 疑似科学は科学の権威だけを借りて、査読や検証といった学術コミュニティーの規範に従わないため、通常の科学の方法で批判しにくい構造がある。
- 疑似科学はしばしば社会的に望ましい目的(教育・福祉・環境など)と結びつくため、批判がその目的への攻撃と受け取られやすい。
- 疑似科学を批判する際には、自らの専門領域を明確にしたうえで、伝統的な知恵や社会的な価値観に不用意に踏み込まないことが重要である。
🖊️技術と人のイノベーションをめぐる、専門家との議論に参加しましょう!


大阪大学社会技術共創研究センター講師。専門は倫理学、特に幸福論や人生の意味、先端科学技術のELSI(Ethical, Legal and Social Issues 倫理的・法的・社会的課題)。最近の業績に”Addressing trade-offs in co-designing principles for ethical AI”, AI and Ethics, vol.4-2, (A. Katiraiとの共著、2024)、R.ハルワニ『愛・セックス・結婚の哲学』(共訳、名古屋大学出版会, 2024)など。
プロフィール詳細
疑似科学批判を、科学者だけに任せておけないのはなぜ?
科学は個人の天才的発見だけで動いているわけではない。現実には科学は共同的・集団的な営みである。
研究論文は(多くの場合)同じ分野の専門家(ピア)による「査読(ピア・レビュー)」を経て学術誌に掲載される。査読者は論文の新規性、方法、データ、結論の妥当性を匿名で厳しくチェックし、不適切とみなされれば掲載を拒否される。また、掲載された研究も他の研究者による追試や批判にさらされ、間違いがあれば訂正や撤回が行われる。
こうした仕組みにより、科学的知識の質が保たれている。
しかし、この「仲間うち(ピア)」のチェックが機能するのは、当然ながら参加者全員が同じルールに従う学術共同体の内部に限られるということはもっと意識されるべきだ。
疑似科学は「科学者のルール」には従わない
疑似科学は、学術共同体の内部ではなくその境界線上で活動していることが多い。
疑似科学的な主張を行う者は、しばしば「○○学会で報告済み」と権威づけを行うが、学会発表は査読論文とは異なり、発表内容の妥当性を保証するものではない。多くの学会は研究成果の交流の場であり、発表された内容が必ずしも科学的に正しいことを担保しているわけではない。
また、「特許出願中」や「特許取得済み」といった文言も科学的正当性の証明にはならない。特許制度は新規性・進歩性・産業上の利用可能性を審査するものであり、科学的な妥当性や効果の実証を求めるものではない。
それどころか、特許権のような知的財産権や競争上の優位性を理由として、技術の詳細な説明や検証可能なデータの公開を拒むことも多い。これは真っ当な科学の特徴である「公開性」と「相互検証」に反する行為である。
つまり、疑似科学は科学の「装い」は借りるが、科学を科学たらしめている「コミュニティの規範」には従わない。査読による品質保障も、追試による検証も、批判への応答義務も回避しながら、科学的権威だけを利用する。
これが科学者コミュニティからの批判を困難にしている。
科学者が疑似科学を批判しにくい理由とは
したがって、科学者が疑似科学を批判しようとすると、いくつかの問題に直面することになる。...