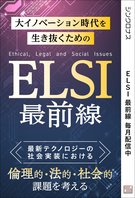毎月メール配信する「ELSI最前線 Newsletter」では、読者の方からのオピニオン投稿を紹介、記事執筆者による応答をお届けしています。今回はその一部を特別公開します。(投稿時に掲載許可を頂いた投稿のみ公開しています)
🖊️技術と人のイノベーションをめぐる、専門家との議論に参加しましょう!

Discussion Forum
読者の方から寄せられた、ELSIに関する意見・質問などの投稿をご紹介。記事執筆者からの応答をお届けします。
小波秀雄さん(京都女子大学名誉教授)
長門裕介さんの「日常に侵入する疑似科学」を興味深く読みました。 私自身も物理・化学の研究者および教育者として長い間ニセ・疑似科学を告発する活動に従事していますので,共感するところが大です。 記事で取り上げられている「電磁波で錆を防ぐ謎の装置」「水と空気から軽油ができた(大阪市協賛の実証実験)」等々については,消費者団体や大学の公開講座での講演を行っています。 https://konamih.sakura.ne.jp/Events/
今回の短期連載では,科学者や理科教育関係者とは専門領域の異なる倫理学の研究者から問題が提起されて,私としては社会的な訴求力がより立体的になってきたと歓迎しています。一方でいろいろと考えることも多くありますので,今後なんらかの形で意見の交流を進めていけないだろうかとも期待しております。
📬応答します(文・長門裕介)
多年にわたりニセ科学に関する情報発信や科学リテラシー教育に携わってこられた小波秀雄先生にお読みいただき、たいへん嬉しく思っています。YouTubeでの活動も拝見しています。
私の学問的なバックグラウンドは倫理学ですが、疑似科学の問題に関心をもつに至った経緯についてここで書いてみることにします。
まず、技術開発の最先端にいる科学者やエンジニアは疑似科学の問題を認識しているのにそれにどのように対応すればいいか迷ってる状況に気づいたことです。
現在、量子コンピューターの社会的影響を調査する研究グループに入っており、量子技術の研究者と話す機会があります。彼らは量子力学や量子技術が一般に難解だと思われてるだけでなく、「引き寄せの法則」などのスピリチュアルな思想や「量子〇〇」と名付けられた怪しげな商品について認識していましたが、それにどうリアクションしていいかは決めかねている様子でした。
また、ときおり科学者・エンジニアのなかにもこうした問題に関心をもつ人がいても、過度に嘲笑的なやり方になったり、〇〇警察と揶揄されるような重箱の隅をつつくような細かいとこに固執してしまう人がいるというような問題が表明されることもありました。
こうした意見を伺うにつれ「疑似科学批判は科学者にとって義務なのか」「どのような条件のもとに疑似科学に対して非難・制裁することが許容されるのか」といった問題に関心をもつようになりました。行為に関する義務や非難の条件整理は一応倫理学の守備範囲なので、疑似科学についてもそうした角度から研究できると思いました。
もうひとつの理由は、...