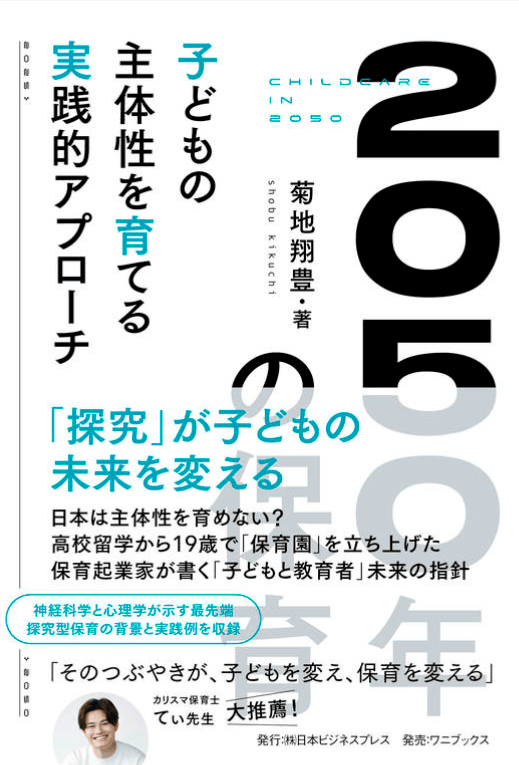これからの保育に必要なのは、子ども一人ひとりの「考える力」と「自分らしさ」を伸ばすことだ。
「世界に一つだけの保育園創り」を掲げた保育園事業「エデュリー」の運営、そして本書の著者である菊地翔豊氏が作ったのは、子どもの疑問や好奇心から学びを広げる「探究型保育」。
様々なエビデンスをもとに作り上げた探究型保育は、自己肯定感や社会性といった“非認知能力”の発達にも効果をもたらすという。
今回は、8月27日(水)発売予定の『2050年の保育 子どもの主体性を育てる実践的アプローチ』より、「探究型保育」が子どもに与えるメリットを紹介していく。

探究型保育にあるエビデンス
新しい時代の変化に伴い求められたのが、個々の子どもの思考力や独自性を伸ばす保育であり、私たちの言う「探究型保育」になります。
改めて、どこにその価値があるのでしょうか。まずいくつかの研究発表を紹介します。
探究型の活動を経験した子どもには、「認知的なスキル(基礎学力や思考力や問題解決力)」が伸びるという結果が報告されています。
具体的な内容は以下の通りです。
より深い概念の理解が促され、学んだ知識同士を結びつけて考える力が高まります。例えば、子どもたちは単なる暗記ではなく、物事の関連性を自ら発見しやすくなることが示されています。
●問題解決力・応用力の向上
習得したスキルを新しい課題に転用する力(汎用的な問題解決力)が高まるとの報告があります。探究的な学びにより、子どもは未知の問題に直面しても過去の経験を活かして解決策を考え出す力を養います。
●知識の定着と想起
文部科学省の報告では、探究的な活動を取り入れることが子どもの知的好奇心を刺激し、学習意欲を高めるだけでなく、知識・技能の定着や活用を促進することが指摘されています。子ども自身が試行錯誤しながら発見するプロセスを通じて学ぶことで、習得した知識が長期的に保持され、必要なときに思い出しやすくなる(知識の想起力が高まる)ことが示唆されています。
学力(リテラシーや数的能力)に関しても、劣らないかそれ以上の成果が得られるというエビデンスがあります。
3~8歳児を対象にした17件の研究レビューでは、子どもが教師に一方的に教わるのではなく、目的を持った遊び(ガイド付きの遊び)に取り組んだ場合、
読み書き能力や実行機能について直接指導と同等かそれ以上の習得が見られたと報告されています。
特に数的概念では、図形の知識など一部の領域で探究遊びをした子どもの方が高い理解を示し、またタスクの切り替え(状況に応じて行動を変更できる認知的柔軟性)といった行動スキルも向上していました。
これらは幼児期の探究的な遊びや環境が、後の学業成功にとって重要な基礎学力や認知能力を育むことを示唆しています
非認知スキルとは?
さらに探究型保育は、「認知的スキル」だけでなく、昨今より注目を集めるようになった、知能検査(テスト)などでは測れないスキル「非認知的スキル」(情動や社会性に関わる能力)の発達にも良い影響を与えることが示されています
中でも子どもの自己肯定感や意欲、共感、感情調整力、社会性といった側面で、探究型のアプローチは従来型より有利に働く可能性が指摘されています。
まず「非認知スキル」について、私たちの園での出来事をもとに解説をします。
ある保育園で、子どもたちが「なぜ、ありさんは列になって歩いているの?」と疑問を口にしたのがきっかけで、虫コーナーができて、虫の行動を探究するプロジェクトがスタートしました。
子どもたちは地域で虫を採取して観察し始め、保育士が調べた図鑑や専門書を一緒に見ながら「ありが行列をつくる理由」を推測したり、匂いの道(ありは道しるべとしてフェロモンを出す)について学んだりしました。
3歳児から5歳児の中で虫に興味のある子たちが一緒になって取り組むプロジェクトを通じて、上の年齢の子が下の子をリードする場面も自然に生まれ、子ども同士が教え合う姿が見られるようになりました。
このように保育の中で協調性やリーダーシップが育っていきます。
こうした体験を重ねるうちに、最初は恥ずかしがり屋だった子どもも「もっと見つけたい ! 」「どうやって調べる ? 」と自分から質問を発し、保育士と一緒に課題を整理できるようになっていきます。
この「自分で疑問を持ち、それを解決しようとする力」は、重要な能力ですがテストなどではなかなか測れませんし、身につけることもできません。
まさに、非認知能力だと言えます。
探究型が育てる3つの非認知能力
では、探究型保育でどのような「非認知能力」が育まれるのでしょうか。
私がこの保育を進める中で大事にした3つの能力を紹介したいと思います。
一つ目が、好奇心や主体性への効果です。探究活動では子ども自らが質問を立てたり仮説を試したりするため、学習への意欲(モチベーション)が高まり、知りたいという好奇心が一層刺激されます。
あるレビュー研究でも、探究学習の導入によって子どもの学習意欲が向上し、学びに対する前向きな態度変容が見られたと報告されています。
また、オーストラリア政府の報告によれば、探究型の「探索」活動を通じて好奇心や粘り強さ(レジリエンス)、楽観性が育まれるとされています。
自分で試行錯誤する経験の中で「もっと知りたい」「失敗してもまた挑戦したい」という態度が培われ、困難に直面しても心が折れにくいレジリエンスにつながるのです。
次に、自己制御や感情面への影響です。発達心理学者のヴィゴツキーも指摘したように、遊びを中心とした活動は子どもの自己認識や自己調整力(自己制御能力)の発達に大きく寄与します。
自由な遊びや探究の過程では、子どもは自分のやりたいことを調整したり、ルールを作って守ったり、感情をコントロールするといった練習を自然に行っています。その結果、感情のコントロールや注意力の持続といった能力が育ちやすくなります。
三つ目に、社会性や対人スキルの面でも恩恵があります。
探究型の保育環境では、子ども同士が協力し、話し合ったりする機会が多く、生きた社会的学習の場となります。
共同作業やディスカッションを通じて、コミュニケーション能 力や共感性が養われるほか、自分の考えを伝え相手の意見を聞く態度が育ちます。
研究によれば、遊びを媒介とした介入は友人関係を築くのが難しい子どもに対しても有効な支援となり、ポジティブな仲間関係スキルの発達を促すことが示されています。
このように探究型保育は、自己肯定感の向上(自分はできるという感覚)や社会的スキルの獲得にも寄与し、非認知的能力全般をバランス良く伸ばす土台となるのです。
第2章(「子どもの力を最大化する保育とは」)でも示した通り、人生の最初の数年間である乳幼児期は、人間の発達において極めて重要な時期です。(続く)
『2050年の保育』(第3章「探究型保育」これまでとどう違う?」)より
【現役保育士・てぃ先生推薦!!】 子どもの能力を最大化させるヒントが満載、注目の保育実践とメソッド