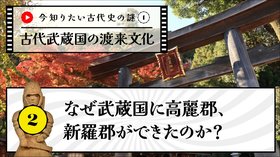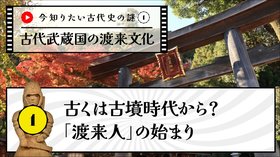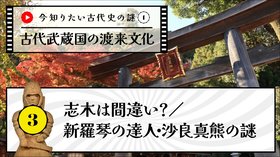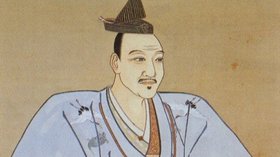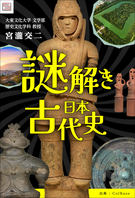日本古代史の専門家が、研究の最前線を紹介する「謎解き古代史」。音声でわかりやすく解説するシリーズ「今知りたい古代史の謎」、初回は「古代武蔵国の渡来文化」を紹介します。
663年の白村江の戦いで、倭国、すなわち後の日本と、660年に唐と新羅の連合軍に滅ぼされた百済遺民との連合軍は、再び唐と新羅の連合軍に敗れ、日本には多くの百済人が渡来します。彼らは現在の大阪にあたる摂津国に移り住み、この地は後に百済郡という郡になります。さらに今度は渡来していた高句麗人、新羅人に対して、朝廷は彼らの住まう場所を武蔵国(現在の東京、埼玉・神奈川の一部)に決め、それぞれ「高麗郡」「新羅郡」と名づけます。
なぜ彼らは、朝廷のある五畿(平城京を取り巻く大和国・山城国・河内国・摂津国・和泉国の5国)からはほど遠い武蔵国に住まわせられたのでしょうか? そもそも渡来人はいつから日本にやってきたのでしょうか? 日本から渡来した人物はいるのでしょうか?
第3回は、現在の新羅郡に位置する埼玉県志木市の「志木」という名前の由来、渡来人のひとりだった沙良真熊という新羅琴の達人についてご紹介します。
*第1回「古くは古墳時代から?知っているようで知らない「渡来人」の始まり」は無料でお楽しみいただけます!
*第2回「なぜ武蔵国に高麗郡、新羅郡ができたのか?」はこちらからお読みいただけます
今回の古代武蔵野国に高麗郡、新羅郡がなぜあるかという話なんですが、今までお話してきたことを簡単にまとめますと、これは武蔵国の郷土史の問題ではなくて、当時の日本と中国、朝鮮半島を統一した新羅との外交問題の1つの結果として生まれたものであるということをお話ししてきました。
中国が皇帝を中心とする中華思想を持っているのと同じように、日本も天皇を中心とする日本型の中華思想を持っていて、敵国である新羅や高句麗の渡来人たちは決して優遇することなく、その当時の日本という国のエリアの、北の最果ての場所の関東に彼らが住む場所を理念的に与えているという、そういうことを中国の皇帝の前で説明したかったんだろうと思います。
そういうことを最近の研究成果を使って簡単にご説明してきました。ここからはそういうことを踏まえて、いくつか面白い話がありますので、古代史は決して今から1300年前の古い話ではなくて、1300年経った今とも非常に関わっているということを、さらにこう皆さんに知っていただくためのエピソードに移っていきたいと思います。
新羅が新座に
武蔵国の新羅郡が現在あった場所には埼玉県の新座(にいざ)市、志木(しき)市、和光市、朝霞市があるわけですけども、新座という字は、新しいに座席の座と書きますが、実はこれは先ほどの古代武蔵国の新羅郡が、平安時代の終わり頃に「羅」の字が「座」の字に変わって「新座郡」となったことに由来しているんですね。
おそらくこれはもう敵国の名前をつけるのはいい加減によそうと、その必要がなくなったということで新しく「新座」という字に変えたのだと思います。ただ、読み方は「にいくら」と、当時の地名辞典にはルビが振ってあります。
そして、この「にいくら」という音が別の字で生きているのが和光市なんですね。まさに「新」に鎌倉の「倉」を書いた和光市「新倉」という地名が和光市に残っています。それから、和光市には、「白」に子どもの「子」と書いて「白子(しらこ)」という場所もあります。これは、しらぎ→しらく→しらこと転じて出来た地名だと思います。新羅は後でお話ししますように、当時の辞書には、「志」に音楽の「楽」を書いて「志楽」とするパターンが結構出てくるんですね。ですから、それを「しらく」と読めば白子につながってくるわけですね。
ということで、地名っていうのはなかなか古代史をやってますと皆さんからご質問を受けるんですけども「古代のこういう地名から来てるんではないでしょうか」とかね。もうこれはなんとも言えませんが、途中をつなぐものがちゃんとあれば、そう、ちゃんと古代から繋がってる可能性があるんですね。いずれにしても、この新座市の新座という字、先ほどの和光市の新倉や白子というのは、どうも新羅から来てることは間違いないと思います。
「志木」の本来の名前は?
さて、志木市の話なんですが、この「志木」という字は実は決して古い地名ではないんですね。現在の志木市の名前は、明治7年(1874)9月に武蔵国の新座郡の引又町(ひきまたまち)と舘村(たてむら)が合併したときに、なんかいい名前がないかと当時の人たちが考えたわけですね。合併して引又にすれば舘村の人は怒るし、舘村の人はね、 舘村とつけたいんでしょうけど、引又の人が怒っちゃうわけですね。そこで古い本を調べて、昔からこのあたりを指した地名をつけようではないかと考えたわけですね。
そして、平安時代にできた『和名類聚抄』という百科全書があるんですけど、そこに当時の全国の国名や郡名の一覧が出ているんですが、そこにこの武蔵国の新倉郡に「志木郷」という、今のこの志に木とかく、東武東上線の駅の名前にもなっているこの文字を見つけたわけですね。そうだ、これで行こうということで、明治7年に引又町と舘村の皆さんは、合併にあたって志木宿という字を付けたんですね。この志木宿が志木市になって今に繋がっているわけです。
ところがですね、学問というのは残酷というか素晴らしいというか、研究が進みまして、この平安時代の『和名類聚抄』という辞書に載っていた志木という字がどうも誤りだということが最近分かってきたんですね。
...