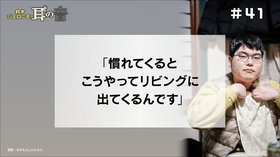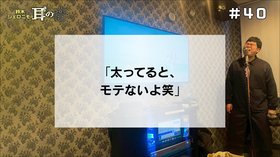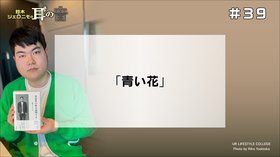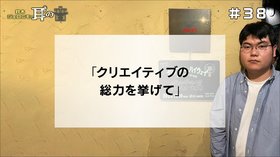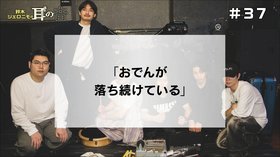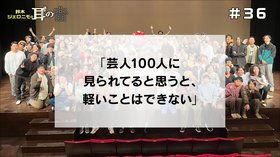街を歩いていると、不意に耳に入ってくる言葉がある。誰かの会話、カフェのBGM、看板の文字。芸人・鈴木ジェロニモが、日常の中で出会った“ちょっと気になる言葉”に耳をすませて、思考を巡らせます。(連載の詳細はこちら)
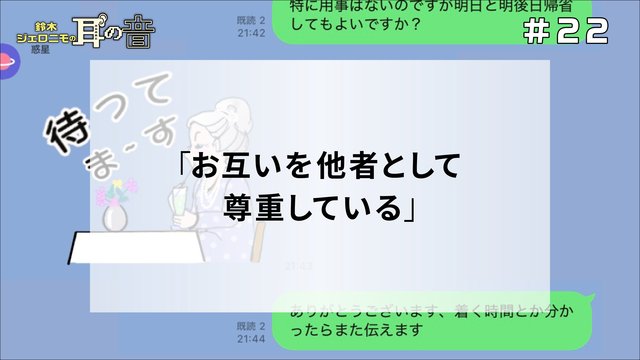
みじかく帰省した。どうやら世間がお盆休みっぽいという印象を得て数日後、あれここちょうど帰省できるんじゃね、というタイミングを見つけて連絡する。特に用事はないのですが明日と明後日帰省してもよいですか。「待ってまーす」。スタンプで返される。ありがとうございます、着く時間とか分かったらまた伝えます。
家族とのLINEが敬語になる。理由は、年上だから。Podcastなどではそう話していた。しかしさすがにねえもうそういうのやめようよ分かったからさ、みたいなのも感じる。改めて、家族とのLINEが敬語になる理由について考える。LINEの歴史が家族よりも後に始まっているから、ということが思い当たる。...