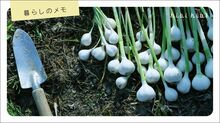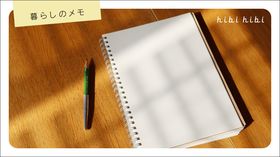急に肌寒くなってきましたね。夜、布団の中に湯たんぽを仕込むシーズンの到来に、寒い季節の幸せを感じます。湯たんぽの、あのじわじわと伝わる温もりは、本当に心がほどけます。布団の中が温泉のようで、自然と身体の力が抜けてリラックス〜。

さて、前回の話は、わたしが自分と向き合う中で、実践したことをいくつかご紹介したのですが、今回はその後編を。
10年前くらいに、まずやってみたことは……
・本を読むこと
・自然を感じる
・身体にいいことをする
・頭の中を整理する
でした。
「本を読むこと」「自然を感じる」は前回の暮らしメモで。たくさんの本を読み、登山と畑を通して自然に触れたことで、わたしの内側が少しずつ変化していったのでした。
前回の記事を読む

「冷えとり」は心の毒出し
それに加えて実践したことは、“冷えとり健康法”です。
ズバリ、身体にいいことをしたくなったのです。頭寒足熱を基本の考えとした健康法なのですが、その教えが書かれた本を読んでいると、しきりに「身体が冷えている=心が冷えている」といったようなワードが出てくるのです。この考え方が、なんだかとても腑に落ちて。
なぜなら、自分と向き合っていくうちに、「心と身体はつながっているなあ」と思うようになっていったからです。
当時、今この瞬間にある幸せを感じられなくなっていたため、わたしの心は疲弊していました。でも、登山や畑で自然に触れるうちに、心が元気になっていき、“自分の中の自然”にも興味を覚えるようになっていたのです。
ここで言う“自分の中の自然”というのは、自分の身体のことです。
登山や畑を通して、自然を近くに感じるたびに、身体と心が癒されていくのを感じていたのですが、癒されるというか、整えてくれるイメージに近いかもしれません。自分の心をちょうどいいバランスに調律するような。濁っていた川が浄化されて澄んでいくような。
心が心地いいと、リンクするように身体も整うのです。
そんな実感があったからこそ、もっと身体を大切にしたいとやってみた“冷えとり健康法”。
でも実は、最初はこの方法を疑っていました。
今まで聞いたこともない、ちょっと変わった方法だったし、周りでやっている人もいないし「本当に効果があるのだろうか? 騙されていない?」と。今思うと、あの頃は何でも疑ってばかりいましたね(笑)。
そして、これが“失敗したくない”“裏切られるのが怖い”という、“心の冷え”だったのです。
それに気付いたのは、冷えとり健康法をやっていくうちに、身体と心が癒えてきてから。「ああ、あの時の恐れや不安は、心が安心を手にしていなかったからだ」と、わかりました。
ここで、遅くなりましたが、冷えとり健康法がいったいどんなものなのか、ちょっとだけご紹介しますね。
まず、この健康法の一番の特徴、それはなんといっても「靴下を重ねばきすること」なんです。変わっていますよね〜。
絹の靴下と木綿の靴下を交互に重ねばきをして、とにかく足元を冷やさないようにする、という一見変わった養生法なのですが、体感イメージとしては、温泉の足湯にずっと浸かっているような感じです。
足湯をしたことがある方は分かるかもしれません。「ふあ〜」と、余計な力が抜けて、安心感に包まれるあの感じ! 足元の温かさが、ただただ心地よい。そんな安心が、靴下の重ねばきをすることによって、日常の中に溶け込み、ガチガチに凍っていた心がほどけていったのです。
冷えとりを始める前のわたしは、もう本当に、身体は冷えていましたし、心も冷えていました。家族からは氷の手足と言われるくらい。わかりやすく言うと、冷え性の症状ですかね。
それが、冷えとり健康法に出会って、のめり込んでいくうちに、...