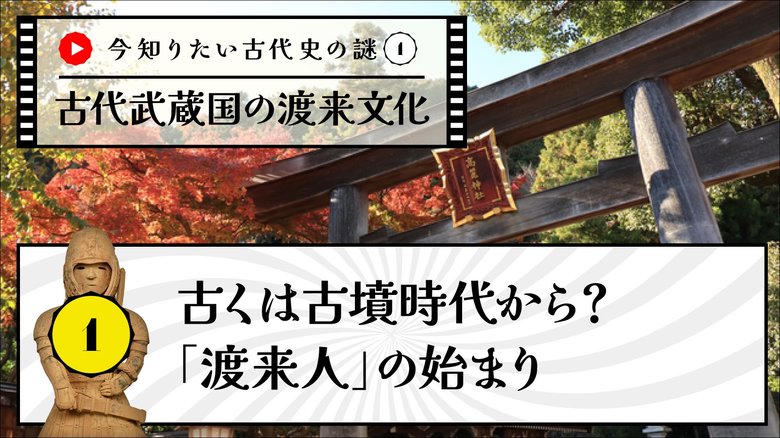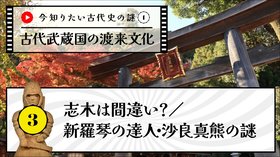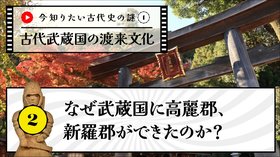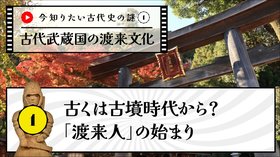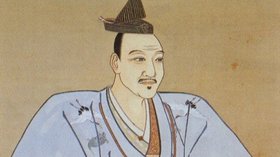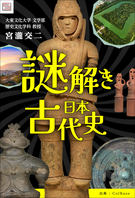日本古代史の専門家が、研究の最前線を紹介する「謎解き古代史」。音声でわかりやすく解説するシリーズ「今知りたい古代史の謎」、初回は「古代武蔵国の渡来文化」を紹介します。
663年の白村江の戦いで、倭国、すなわち後の日本と、660年に唐と新羅の連合軍に滅ぼされた百済遺民との連合軍は、再び唐と新羅の連合軍に敗れ、日本には多くの百済人が渡来します。彼らは現在の大阪にあたる摂津国に移り住み、この地は後に百済郡という郡になります。さらに今度は渡来していた高句麗人、新羅人に対して、朝廷は彼らの住まう場所を武蔵国(現在の東京、埼玉・神奈川の一部)に決め、それぞれ「高麗郡」「新羅郡」と名づけます。
なぜ彼らは、朝廷のある五畿(平城京を取り巻く大和国・山城国・河内国・摂津国・和泉国の5国)からはほど遠い武蔵国に住まわせられたのでしょうか? そもそも渡来人はいつから日本にやってきたのでしょうか? 日本から渡来した人物はいるのでしょうか?
3回に渡り、解説します。
*初回無料、今回は記事でもお楽しみいただけます!
こちらの音声は以下の商品の中に含まれております。
ご購入いただくと過去記事含むすべてのコンテンツがご覧になれます。
ご購入いただくと過去記事含むすべてのコンテンツがご覧になれます。
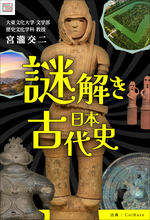
日本古代史の専門家が、研究の最前線を紹介する「謎解き古代史」。記事と音声でわかりやすく解説するシリーズ「今知りたい古代史の謎」、今回は「古代武蔵国の渡来文化」を紹介します(全3回)。
【無料】(1)古くは古墳時代から?「渡来人」の始まり
(2)なぜ武蔵国に高麗郡、新羅郡ができたのか?
(3)「志木」という地名は間違い?/新羅琴の達人・沙良真熊の謎
ログインしてコンテンツをお楽しみください
会員登録済みの方は商品を購入してお楽しみください。
会員登録がまだの方は会員登録後に商品をご購入ください。
会員登録がまだの方は会員登録後に商品をご購入ください。