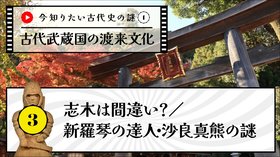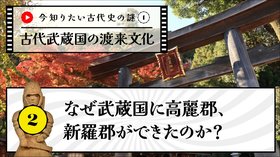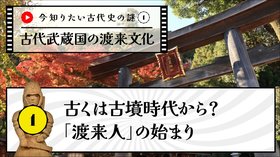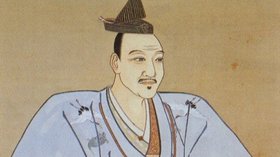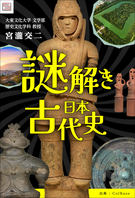日本古代史の専門家が、研究の最前線を紹介する「謎解き古代史」。音声でわかりやすく解説するシリーズ「今知りたい古代史の謎」、初回は「古代武蔵国の渡来文化」を紹介します。
663年の白村江の戦いで、倭国、すなわち後の日本と、660年に唐と新羅の連合軍に滅ぼされた百済遺民との連合軍は、再び唐と新羅の連合軍に敗れ、日本には多くの百済人が渡来します。彼らは現在の大阪にあたる摂津国に移り住み、この地は後に百済郡という郡になります。さらに今度は渡来していた高句麗人、新羅人に対して、朝廷は彼らの住まう場所を武蔵国(現在の東京、埼玉・神奈川の一部)に決め、それぞれ「高麗郡」「新羅郡」と名づけます。
なぜ彼らは、朝廷のある五畿(平城京を取り巻く大和国・山城国・河内国・摂津国・和泉国の5国)からはほど遠い武蔵国に住まわせられたのでしょうか? そもそも渡来人はいつから日本にやってきたのでしょうか? 日本から渡来した人物はいるのでしょうか?
第2回は、武蔵国にできた経緯に迫ります。
*第1回「古くは古墳時代から?知っているようで知らない「渡来人」の始まり」は無料でお楽しみいただけます!
...