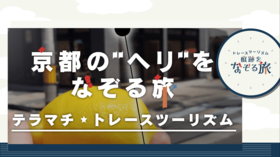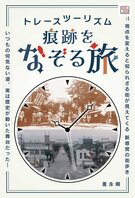過去の人々が見た景色や感じた空気を追体験する新しい旅の形「トレースツーリズム」。地図やガイドにも載らない、街歩きの面白さを『Y字路はなぜ生まれるのか?』(晶文社)の著者・重永瞬さんが解き明かす―新連載がスタートします!
▼連載の詳細はこちら


京都府出身。京都大学大学院文学研究科地理学専修に在籍(博士課程)。専門は歴史地理学。縁日露店の歴史について研究するかたわら、まち歩き団体「まいまい京都」でツアーガイドを務める。 著作に『Y字路はなぜ生まれるのか』(晶文社)、『統計から読み解く色分け日本地図』(彩図社)など。 奈良新聞にて連載「大和参道紀行」を担当(2024年6月~2025年6月)。
旅日記に残された足跡を追う
前回の記事では、街道や参道を例として、トレースツーリズム=「なぞる」旅の楽しみ方を紹介した。
古い道を歩くことで、かつての旅人の気分を追体験することができる。今回は、この「追体験」をさらに色鮮やかなものにする方法を紹介しよう。
それは、「旅日記」をなぞるという方法である。
古くから、人びとは旅の思い出を日記に記してきた。早いところでは、平安貴族である紀貫之が、土佐から京へ帰る55日間の旅路を『土佐日記』として脚色を交えつつ描いている。
庶民が旅日記を書くようになったのは江戸時代からで、後から旅に出る人の参考になるよう旅の道のりや使ったお金を記載した「道中記」が多く記された。
旅日記は大きく分けると、紀行文のように文学的性格を備えたものと、記録的性格が強いものに分かれる。
紀行文で有名な作品といえば、松尾芭蕉の『奥の細道』が挙げられるだろう。東北から北陸にかけて歩きながら、先々で俳句を詠んだ芭蕉の代表作だ。「閑さや岩にしみ入る蝉の声」や「五月雨をあつめて早し最上川」など、登場する句の風景は今もたどることができる。
しかし、約2400kmにもわたるその道のりをすべてなぞることは容易ではない。
そこで、今回はもう少し身近なスケールで足取りをなぞれる日記を取り上げたい。
本居宣長が何度も訪れた京都
今回取り上げるのは、江戸時代の国学者、本居宣長の日記である。
伊勢国松坂に生まれた宣長は、20代後半の2年間、京都に滞在し、医者になるための勉強をしていた。宣長は日々の生活を事細かに書き記し、『在京日記』としてまとめている。...